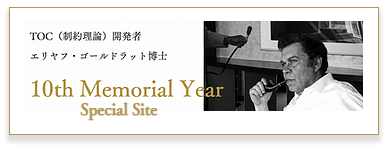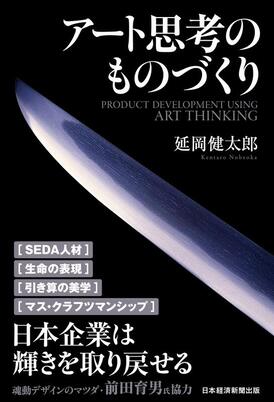iPS細胞が拓く新しいがん治療 免疫再生研究と産業化の取り組み
2024年4月18日、京都大学iPS細胞研究所は、iPS細胞を活用した新たながん治療方法の確立と普及を目指す「My T-Serverプロジェクト」の発足を公表しました。
がん治療に使えるiPS細胞を作製する小型の培養装置「My T-Server」を開発するプロジェクトで、パナソニックHD、シノビ・セラピューティクス社とともに、大阪・関西万博が開催される2025年4月までに試作機を完成させることを目指されています。
▼iPS細胞を活用した新たな個別化がん治療方法を確立・普及するためのプロジェクトを発足
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/240418-150000.html
そこで今回のTOCクラブでは、このプロジェクトを主導する京都大学iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門の代表である金子新教授を特別にお招きし、「My T-Server」を支える免疫再生研究と産業化を目指す取り組みについてお話いただきます。
iPS細胞を用いた個別化がん治療が身近なクリニックで安価に受けられる日をいち早く実現する世界最先端の研究開発にTOCがどのように活用されているのか、現在そしてこれからのiPS細胞研究がどのような未来を描いていくのか、ここでしか聞けない貴重なお話をご講演いただきます。
がん治療に使えるiPS細胞を作製する小型の培養装置「My T-Server」を開発するプロジェクトで、パナソニックHD、シノビ・セラピューティクス社とともに、大阪・関西万博が開催される2025年4月までに試作機を完成させることを目指されています。
▼iPS細胞を活用した新たな個別化がん治療方法を確立・普及するためのプロジェクトを発足
https://www.cira.kyoto-u.ac.jp/j/pressrelease/news/240418-150000.html
そこで今回のTOCクラブでは、このプロジェクトを主導する京都大学iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門の代表である金子新教授を特別にお招きし、「My T-Server」を支える免疫再生研究と産業化を目指す取り組みについてお話いただきます。
iPS細胞を用いた個別化がん治療が身近なクリニックで安価に受けられる日をいち早く実現する世界最先端の研究開発にTOCがどのように活用されているのか、現在そしてこれからのiPS細胞研究がどのような未来を描いていくのか、ここでしか聞けない貴重なお話をご講演いただきます。
2024年5月30日【オンライン】
世界最大の消費財会社P&Gが実践するDX成功に不可欠なシンプルな問いとは?
今回のTOCクラブは、TOCを用いたDXで飛躍的な成果をあげた、世界最大の消費財会社である米国P&Gの成果事例をご紹介します。
P&GではIT部門におけるCCPM導入からスタートし、
・開発期間が3~4割短縮
・3ヶ月で山積みのバックログが解消
・スループットが25%増加
といった成果が上がりましたが、その取り組みはトップダウンの押し付けではなく、現場との対話、合意形成からはじまった、まさに文化の変革へのチャレンジでした。
今回は、この経験から得られた「DX成功に不可欠なシンプルな問い」を軸に、"なんちゃってDX”に陥らず、たしかに成果を上げるために問うべきことは何なのか、組織の変革を後戻りさせることなく、加速し続けるにはどうすればよいのか、ぜひみなさんと議論したいと思います。
DXを担うマネジメントやIT部門の方はもちろん、組織のリーダーとして多くの人を束ね、「問いの力」によって成果を生み出すことを志す全ての方にぜひご参加いただきたい内容です。
P&GではIT部門におけるCCPM導入からスタートし、
・開発期間が3~4割短縮
・3ヶ月で山積みのバックログが解消
・スループットが25%増加
といった成果が上がりましたが、その取り組みはトップダウンの押し付けではなく、現場との対話、合意形成からはじまった、まさに文化の変革へのチャレンジでした。
今回は、この経験から得られた「DX成功に不可欠なシンプルな問い」を軸に、"なんちゃってDX”に陥らず、たしかに成果を上げるために問うべきことは何なのか、組織の変革を後戻りさせることなく、加速し続けるにはどうすればよいのか、ぜひみなさんと議論したいと思います。
DXを担うマネジメントやIT部門の方はもちろん、組織のリーダーとして多くの人を束ね、「問いの力」によって成果を生み出すことを志す全ての方にぜひご参加いただきたい内容です。
2023年12月14日【オンライン】
パーパス経営」名和高司先生―「ワクワク」「ならでは」「できる!」志本経営とは?
「失われた30年」日本は何を間違っていたのだろうか?
今回のTOCクラブでは、グローバルスタンダードという幻想に振り回された「平成30年間の失敗」から日本が再生する道を照らした名著『パーパス経営』の名和先生に「志本経営」の真髄についてお話しいただきます。
ベストセラー『パーパス経営』のユニークなところは、これ一冊で経営学の潮流が豊富な事例とともにわかりやすく理解でき、日本再生の道で様々な知見が得られること。しかも、名和先生のならではのスパイシーで、時には苦笑してしまう以下のようなベタな表現
「グローバルスタンダードという幻想」
「ハードワークこそがヒトを成長させる、などと口走ろうものなら即座にブラック
企業扱いされてしまう」
「欧米の後追いが好きな平成時代の日本」
「会社を投機という金融ゲームの対象としかみてない」
「規定演技をきちんと演じるだけでは独自性も真の競争優位も築きえない」
「化学産業は、炭素を加工して付加価値の高い製品を創り出す『錬炭素術師』」
「Dではなく「X=変革」こそが経営の主軸」
「やってるつもり病」
「POC病」
「出島病」
「風土病」
「舶来病」
「世界標準などどこにも存在しない」
などなど、経営学の最先端の知見に触れながらも、日常に活用できる知見を我々に提供してくれます。
名和先生は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられた1980年台アメリカ東海岸で6年間暮らし、最初の4年間は商社マンとして日本への畏敬と畏怖を味わい、後半の2年間はハーバード・ビジネススクールの教室で日本の成功から何を学ぶべきか世界から集まった英知と日々議論し、その後「失われた30年間」の平成期にアメリカ型金融資本主義に浸食された日本を見てきました。これには以下の3つのエージェント(手先)があると指摘します。
・MBAを輩出するビジネススクール
・外資系コンサルティング会社
・旧態依然とした日本的経営を叩く一方で、アメリカ流の経営手法を称賛するマスコミ
名和先生の「パーパス経営」とは会社の高い志を中心に据えた、いわば”志本経営”と呼ぶべきもので、今後30年、資本主義の次を見据えたときに新時代の核心をなす考え方。
”志本経営”とはどのような経営のあり方なのか、経営に取り入れる上でどのようなポイントがあるのか、そして、日本企業が「失われた30年」を巻き返して大きく飛躍するためにいま何をすべきなのか、国内外の数多くの企業を飛躍に導いてきた名和先生だからこそ語れる企業経営、組織改革の実際をお話しいただきます。
「目標達成を阻む最大の障害は、目標を低く設定しすぎることである」
高い目標を設定することの重要性はゴールドラット博士も語る通りで、全体最適のマネジメント理論TOCを実践する上で最も大切なことだと言っても過言ではありません。
今回のTOCクラブでは、グローバルスタンダードという幻想に振り回された「平成30年間の失敗」から日本が再生する道を照らした名著『パーパス経営』の名和先生に「志本経営」の真髄についてお話しいただきます。
ベストセラー『パーパス経営』のユニークなところは、これ一冊で経営学の潮流が豊富な事例とともにわかりやすく理解でき、日本再生の道で様々な知見が得られること。しかも、名和先生のならではのスパイシーで、時には苦笑してしまう以下のようなベタな表現
「グローバルスタンダードという幻想」
「ハードワークこそがヒトを成長させる、などと口走ろうものなら即座にブラック
企業扱いされてしまう」
「欧米の後追いが好きな平成時代の日本」
「会社を投機という金融ゲームの対象としかみてない」
「規定演技をきちんと演じるだけでは独自性も真の競争優位も築きえない」
「化学産業は、炭素を加工して付加価値の高い製品を創り出す『錬炭素術師』」
「Dではなく「X=変革」こそが経営の主軸」
「やってるつもり病」
「POC病」
「出島病」
「風土病」
「舶来病」
「世界標準などどこにも存在しない」
などなど、経営学の最先端の知見に触れながらも、日常に活用できる知見を我々に提供してくれます。
名和先生は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられた1980年台アメリカ東海岸で6年間暮らし、最初の4年間は商社マンとして日本への畏敬と畏怖を味わい、後半の2年間はハーバード・ビジネススクールの教室で日本の成功から何を学ぶべきか世界から集まった英知と日々議論し、その後「失われた30年間」の平成期にアメリカ型金融資本主義に浸食された日本を見てきました。これには以下の3つのエージェント(手先)があると指摘します。
・MBAを輩出するビジネススクール
・外資系コンサルティング会社
・旧態依然とした日本的経営を叩く一方で、アメリカ流の経営手法を称賛するマスコミ
名和先生の「パーパス経営」とは会社の高い志を中心に据えた、いわば”志本経営”と呼ぶべきもので、今後30年、資本主義の次を見据えたときに新時代の核心をなす考え方。
”志本経営”とはどのような経営のあり方なのか、経営に取り入れる上でどのようなポイントがあるのか、そして、日本企業が「失われた30年」を巻き返して大きく飛躍するためにいま何をすべきなのか、国内外の数多くの企業を飛躍に導いてきた名和先生だからこそ語れる企業経営、組織改革の実際をお話しいただきます。
「目標達成を阻む最大の障害は、目標を低く設定しすぎることである」
高い目標を設定することの重要性はゴールドラット博士も語る通りで、全体最適のマネジメント理論TOCを実践する上で最も大切なことだと言っても過言ではありません。
2023年11月15日【オンライン】
2カ月で部分最適の文化を全体最適に変えることは可能か?―先端技術開発におけるマネジメント革新
巨額の予算を投じたITプロジェクト破綻が引き起こした経営危機。この逆境からの飛躍の物語を描き、全米ベストセラーとなった“THE PHOENIX PROJECT”(邦題『The DevOps 逆転だ!』)をご存じでしょうか?
身の回りを見渡せばあらゆる機器はソフトウェアがなければ動かないのが現実。多くの方々がすでにお気づきの通り、ソフトウェアはすでに産業界のボトルネックになっているのは言うまでもありあせん。
この本は、まさにITプロジェクト破綻による経営危機の逆境から飛躍への物語。主人公のビルは、メンターのエリックの助けを得ながら、社内のポリティックスから来る理不尽な要求、次々と起きるトラブル対応の渦中で成長し、会社を飛躍へと導いていきます。
主人公のメンター、エリックは『ザ・ゴール』のジョナそのもの。TOCの考えをITプロジェクトに適用する考え方を紹介しています。
今回のTOCクラブでは、本書の監修者を務められた、パナソニックコネクト株式会社の榊原彰CTOをお招きし、特別にご講演いただきます。
榊原CTOは日本IBMや日本マイクロソフトでCTOを歴任し、日本マイクロソフトの兄弟会社で製品開発に特化したマイクロソフトディベロップメントの社長も兼務された日本を代表するCTOで、今や多くのビジネスパーソンに知られる「DevOps」の考え方を国内に広めた第一人者でもあります。
榊原氏には、本書の解説を通じて、いま改めて「DevOps」とは何なのかをお話しいただき、その源流にはゴールドラット博士のTOCが理論的背景として存在していることなど、さまざまな角度で本書から学ぶべきエッセンスが何なのかを解説していただきます。
身の回りを見渡せばあらゆる機器はソフトウェアがなければ動かないのが現実。多くの方々がすでにお気づきの通り、ソフトウェアはすでに産業界のボトルネックになっているのは言うまでもありあせん。
この本は、まさにITプロジェクト破綻による経営危機の逆境から飛躍への物語。主人公のビルは、メンターのエリックの助けを得ながら、社内のポリティックスから来る理不尽な要求、次々と起きるトラブル対応の渦中で成長し、会社を飛躍へと導いていきます。
主人公のメンター、エリックは『ザ・ゴール』のジョナそのもの。TOCの考えをITプロジェクトに適用する考え方を紹介しています。
今回のTOCクラブでは、本書の監修者を務められた、パナソニックコネクト株式会社の榊原彰CTOをお招きし、特別にご講演いただきます。
榊原CTOは日本IBMや日本マイクロソフトでCTOを歴任し、日本マイクロソフトの兄弟会社で製品開発に特化したマイクロソフトディベロップメントの社長も兼務された日本を代表するCTOで、今や多くのビジネスパーソンに知られる「DevOps」の考え方を国内に広めた第一人者でもあります。
榊原氏には、本書の解説を通じて、いま改めて「DevOps」とは何なのかをお話しいただき、その源流にはゴールドラット博士のTOCが理論的背景として存在していることなど、さまざまな角度で本書から学ぶべきエッセンスが何なのかを解説していただきます。
2023年10月19日【オンライン】
2カ月で部分最適の文化を全体最適に変えることは可能か?―先端技術開発におけるマネジメント革新
トップサイエンティストがグローバル競争でしのぎを削る先端技術イノベーションの特徴は何でしょうか?
・巨額の投資リスクがある
・それぞれの専門分野のエキスパートによる分業作業が欠かせない
・不確実性が極めて高い
近年、激しい技術革新グローバル競争が繰り広げられている、宇宙空間を活用したサービス。そのような環境下において、それぞれのメンバーは頑張っているのに、プロジェクトが大幅に遅れてしまうことは少なくありません。その渦中、責任感の強いメンバーは
それぞれ目の前のことで精一杯になり、疲弊してしまう状態に陥りがちになります。
こんな状況からマネジメント改革に取り組んだ結果、たった2カ月間の取り組みで4カ月の遅れを完全に取り戻すどころか、問題を抱え込み、部分最適に陥りがちな組織風土を一新することに成功し、組織のみんなが助け合い、「働いていて今が一番楽しい」という声が上がる全体最適の組織に変革した事例を紹介します。
ボトムアップでもなく、トップダウンでもなく、自律的にみんなが助け合う楽しい職場をいかに実現するか、今回のTOCクラブは、たった2カ月で起きた組織文化の変化とそれをどうやって引き起こしたかを実例を交えてご紹介します。
プロジェクトマネジメントを担うプロマネの方はもちろん、現場の力を引き出し、組織風土を変えていきたいと願うリーダーや現場を支えるスタッフのみなさんにも非常に多くの学びがあるはずです。
宇宙空間を活用したサービスの現場も垣間見え、変革を実践してきたリーダーの方から直接講演いただく贅沢なセミナーです。
・巨額の投資リスクがある
・それぞれの専門分野のエキスパートによる分業作業が欠かせない
・不確実性が極めて高い
近年、激しい技術革新グローバル競争が繰り広げられている、宇宙空間を活用したサービス。そのような環境下において、それぞれのメンバーは頑張っているのに、プロジェクトが大幅に遅れてしまうことは少なくありません。その渦中、責任感の強いメンバーは
それぞれ目の前のことで精一杯になり、疲弊してしまう状態に陥りがちになります。
こんな状況からマネジメント改革に取り組んだ結果、たった2カ月間の取り組みで4カ月の遅れを完全に取り戻すどころか、問題を抱え込み、部分最適に陥りがちな組織風土を一新することに成功し、組織のみんなが助け合い、「働いていて今が一番楽しい」という声が上がる全体最適の組織に変革した事例を紹介します。
ボトムアップでもなく、トップダウンでもなく、自律的にみんなが助け合う楽しい職場をいかに実現するか、今回のTOCクラブは、たった2カ月で起きた組織文化の変化とそれをどうやって引き起こしたかを実例を交えてご紹介します。
プロジェクトマネジメントを担うプロマネの方はもちろん、現場の力を引き出し、組織風土を変えていきたいと願うリーダーや現場を支えるスタッフのみなさんにも非常に多くの学びがあるはずです。
宇宙空間を活用したサービスの現場も垣間見え、変革を実践してきたリーダーの方から直接講演いただく贅沢なセミナーです。
2023年7月3日【オンライン】
TOC流ゼロからの起業イノベーション "思い込み”さえ解消すれば、すべてがうまくいく
「アイデアは制約ではない。アイデアをビジネスにすることに制約があるのだ」
イノベーション先進国イスラエルで良く使われる言葉です。
いかに優れたアイデアがあっても、それをお金に出来ないとビジネスにはなりません。「儲かるビジネスモデル」がないとベンチャーキャピタルなどから資金調達ができないのは当然ですが、社内起業がうまく行かない理由の多くも同様の理由だと言われています。
そこで、今回のTOCクラブのテーマは、
TOC流ゼロからの起業イノベーション 「思い込み」さえ解消すれば、すべてがうまくいく
と題し、「資金ゼロ、顧客ゼロ、営業経験ゼロ」の逆境から、TOCの「思考プロセス」を駆使することでシリコンバレーからの
投資を獲得し、世の中が驚くような画期的なイノベーションを実現した事例を特別にご講演頂きます。
御存知の通り、起業して事業を立ち上げるためには、多くの障害があります。
仕事が出来ると言われた優秀な人でも、サラリーマン時代の経験がほとんど通用しない様々な障害が次々と起きるスタートアップ企業の立ち上げの中で、世の中が驚くようなイノベーションのアイデアをいかに創り、実現にむけた障害の数々を「思考プロセス」で思い込みを覆すことで次々と解消し、世の中が驚く商品を実現したか、ナマナマしい事例も含めてお話いただきます。
もちろん、このプロセスの中で生まれた画期的な商品もご紹介します。このイノベーションが解消する問題は、個人のお悩みから地球環境の問題まで幅広いもので、当日の発表を楽しみにしていただければと思います。(購入も可能です!)
みなさんも必ず日々活用している「商品」における「常識」を打ち破り、限界を突破するプロセスには多くの学びがあります。
イノベーション先進国イスラエルで良く使われる言葉です。
いかに優れたアイデアがあっても、それをお金に出来ないとビジネスにはなりません。「儲かるビジネスモデル」がないとベンチャーキャピタルなどから資金調達ができないのは当然ですが、社内起業がうまく行かない理由の多くも同様の理由だと言われています。
そこで、今回のTOCクラブのテーマは、
TOC流ゼロからの起業イノベーション 「思い込み」さえ解消すれば、すべてがうまくいく
と題し、「資金ゼロ、顧客ゼロ、営業経験ゼロ」の逆境から、TOCの「思考プロセス」を駆使することでシリコンバレーからの
投資を獲得し、世の中が驚くような画期的なイノベーションを実現した事例を特別にご講演頂きます。
御存知の通り、起業して事業を立ち上げるためには、多くの障害があります。
仕事が出来ると言われた優秀な人でも、サラリーマン時代の経験がほとんど通用しない様々な障害が次々と起きるスタートアップ企業の立ち上げの中で、世の中が驚くようなイノベーションのアイデアをいかに創り、実現にむけた障害の数々を「思考プロセス」で思い込みを覆すことで次々と解消し、世の中が驚く商品を実現したか、ナマナマしい事例も含めてお話いただきます。
もちろん、このプロセスの中で生まれた画期的な商品もご紹介します。このイノベーションが解消する問題は、個人のお悩みから地球環境の問題まで幅広いもので、当日の発表を楽しみにしていただければと思います。(購入も可能です!)
みなさんも必ず日々活用している「商品」における「常識」を打ち破り、限界を突破するプロセスには多くの学びがあります。
2023年4月18日【オンライン】
DXプロジェクトのボトルネックは何か?―イスラエル最大手銀行のDX事例に学ぶ―
「うちの会社のDXプロジェクトは、果たしてうまくいっているのだろうか?」
いまやDXに取り組まない企業はないと言われるほどビジネスの現場に浸透したDXですが、「DXで飛躍的な成果を上げた」という成功例をほとんど耳にしないのは一体なぜでしょうか。
DXプロジェクトの多くが失敗に終わる最大の理由。それは、プロジェクトがDXの"目的"を明確に定義しないまま、「デジタル化」という"手段"に走ってしまうことにあります。
そこで、今回のTOCクラブでは、DXプロジェクトのボトルネックは何か、どうすればDXにTOCを活用し、短期で飛躍的な成果を上げることができるのか、について議論します。
デジタル化という手段が目的化することを防ぎ、DXプロジェクトのボトルネックを徹底活用して成果を上げるには、常に"顧客の視点"を起点にして考えることが重要です。
顧客の視点から最も重要な問題を明らかにし、その解決策をしっかりとオペレーションに落とし込んだ上で、必要な部分に絞ってデジタル化する。
こうしたプロセスについて、今回はイスラエル最大手の銀行のDX事例を題材にしながら詳しく議論します。
今後立ち上げるDXプロジェクトの参考になることはもちろんですが、現在、プロジェクトの建て直しに腐心しているマネジメントの方にこそ、すぐに使える考え方が見つかるはずです。
いまやDXに取り組まない企業はないと言われるほどビジネスの現場に浸透したDXですが、「DXで飛躍的な成果を上げた」という成功例をほとんど耳にしないのは一体なぜでしょうか。
DXプロジェクトの多くが失敗に終わる最大の理由。それは、プロジェクトがDXの"目的"を明確に定義しないまま、「デジタル化」という"手段"に走ってしまうことにあります。
そこで、今回のTOCクラブでは、DXプロジェクトのボトルネックは何か、どうすればDXにTOCを活用し、短期で飛躍的な成果を上げることができるのか、について議論します。
デジタル化という手段が目的化することを防ぎ、DXプロジェクトのボトルネックを徹底活用して成果を上げるには、常に"顧客の視点"を起点にして考えることが重要です。
顧客の視点から最も重要な問題を明らかにし、その解決策をしっかりとオペレーションに落とし込んだ上で、必要な部分に絞ってデジタル化する。
こうしたプロセスについて、今回はイスラエル最大手の銀行のDX事例を題材にしながら詳しく議論します。
今後立ち上げるDXプロジェクトの参考になることはもちろんですが、現在、プロジェクトの建て直しに腐心しているマネジメントの方にこそ、すぐに使える考え方が見つかるはずです。
2022年10月19日【オンライン】
Roland再上場への道のり ー 自分軸を持ち、解き放て!
2020年再上場を果たしたRoland。
世界で1,000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者ゴールドラット博士の10周忌にメモリアルメッセージで三木社長がTOCからの学びを語っているので、ご存じの方も多いと思います。
世界で1,000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者ゴールドラット博士の10周忌にメモリアルメッセージで三木社長がTOCからの学びを語っているので、ご存じの方も多いと思います。
今回のTOCクラブでは、外資系ファンドの支援を得てMBO(Management Buy-Out)を実施し、技術者であった三木さんが社長になり、経営再建し、再上場を果たすまでの道のりで大切にしたこと、効果のあった施策についてお話しいただきます。
三木さんは、楽器のエンジニアですから、プレゼンスタイルも「コール&レスポンススタイル♪」キラ星のごとくキーワードがでてくる言葉は歌詞のよう。そして、自ら脳みそに汗をかいて全体最適の経営改革を実践してきた方ならでは、魂のこもった言葉の数々の力には圧倒されます。
- 「思いが大事」
- 「30年でGDPの成長は米国は4.5倍、欧州各国は2-2.5倍、イタリアは2倍、中国は50倍、日本は1.1倍」
- 「何が日本に欠けているのか?」
- 「イノベーションに欠かせないものーしつこさ」
- 「10年後のWOW!」をみんなで創る
- 「情熱」「謙虚さ」「素直さ」
- 「暴走」か「保身」かー経営トップが陥る罠
- 「スキルセット」よりも「マインドセット」
- 「思いつき」の見える化―フーンで終わる
- 「財務の数字だけで話をしている」では根拠がない
- 「限界利益を全部見える化―全製品で儲かっているのか、儲かってないのか見える化した」
- 「スループット会計で判断する」
- 「本当のボトルネックは何か?」を問うべき
- 「日本の企業は利益率10%できるはず」
- 「在庫は負債―できるだけ早く回す。お金を早く回す」
- 「何のために見える化するかー目標がなければ意味がない」
- 「自分のやりたいことをやりたいーその思いが危機の時に社長となった動機」
- 「新人がTOCを学べば、生産性が1年で2倍、3倍になる」
- 「半年でベテランを追い抜く新人が出てくる」
- 「新人教育はコストセンターではなく、プロフィットセンターになる」
- 「もっとも貴重なのは時間。時間は買えない」
- 「自分には無理だという思い込み」
- 「とにかくやってみるー学べれば楽しい」
三木さんは、楽器のエンジニアですから、プレゼンスタイルも「コール&レスポンススタイル♪」キラ星のごとくキーワードがでてくる言葉は歌詞のよう。そして、自ら脳みそに汗をかいて全体最適の経営改革を実践してきた方ならでは、魂のこもった言葉の数々の力には圧倒されます。
2022年08月08日【オンライン】
納期遵守率とスループットの飛躍的改善:医薬品高難度プロジェクトへのTOCの適用
不確実性の高いプロジェクト環境でも、CCPMによるバッファマネジメントを導入することで、仕事の品質を高めながら納期遵守率を向上させることが可能なのはみなさんご存知のとおりです。
しかし、
そこで今回のTOCクラブでは、「納期遵守率とスループットの飛躍的改善:医薬品高難度プロジェクトへのTOCの適用」と題し、飛躍的な成果を生み出す方法について、成果事例をもとに議論します。
こうした環境で取り組みを進める上で最も重要なヒントは実は、全体最適のマネジメントの公式集と言えるS&Tツリーの中にあります。S&Tツリーの核となるロジックを愚直に実施することで、競争力の源泉になる自社の強みを確立し、組織のコアの対立を解消しながら飛躍的な成果を生み出すことにつながっていきますが、事業の難易度が高ければ高いほど、こうした強みを持つことは他社にとって大きな脅威になります。
今回ご紹介する事例では、取り組み1年で納期遵守率が飛躍的に向上し、顧客からの圧倒的な信頼を得たことで、2年間でスループットを2倍に伸ばすことに成功しています。プレゼンテーションの最後には、ゴールドラット博士本人による解説映像もありますので、ぜひ一緒に学んでいければと思います。
しかし、
- 顧客の要求水準が極めて高い
- 社内の数多くの部署との密な連携が必要不可欠
- 数年スパンの中長期に渡る新規の開発が要求される
- 複雑な規制産業で行政からの監視が強い
- 海外企業との取引が多い
- 大規模な設備投資が欠かせない
そこで今回のTOCクラブでは、「納期遵守率とスループットの飛躍的改善:医薬品高難度プロジェクトへのTOCの適用」と題し、飛躍的な成果を生み出す方法について、成果事例をもとに議論します。
こうした環境で取り組みを進める上で最も重要なヒントは実は、全体最適のマネジメントの公式集と言えるS&Tツリーの中にあります。S&Tツリーの核となるロジックを愚直に実施することで、競争力の源泉になる自社の強みを確立し、組織のコアの対立を解消しながら飛躍的な成果を生み出すことにつながっていきますが、事業の難易度が高ければ高いほど、こうした強みを持つことは他社にとって大きな脅威になります。
今回ご紹介する事例では、取り組み1年で納期遵守率が飛躍的に向上し、顧客からの圧倒的な信頼を得たことで、2年間でスループットを2倍に伸ばすことに成功しています。プレゼンテーションの最後には、ゴールドラット博士本人による解説映像もありますので、ぜひ一緒に学んでいければと思います。
2022年07月27日【オンライン】
2年半で企業価値10倍を実現した逆境からの飛躍法とは?
「かつてない逆境のなか、いかに短期で高い成果を生み出せるか?」
2年半という短い期間で、企業価値を10倍、利益額をなんと25倍ににまで飛躍させた企業があります。競合他社がコロナ禍の逆風で苦戦する中、これだけの飛躍をどのように実現することができたのでしょうか?
ゴールドラット博士は、企業価値を高める3つのステップを明らかにしています。
今回のTOCクラブでは、こうした成果を生み出したロジックを事例とともに、いかに短期で「逆境からの飛躍」を実現するのか、TOC流の企業価値の上げ方をご紹介します。
「モノ言う株主、ファンド、CFOがなぜTOCの最大の応援者になるのか?」
短期間に目覚ましい成果を出し、企業価値を上げる『ザ・ゴール2』に描かれたストーリーの実践のロジックが現実の事例で明らかになる素晴らしい内容です。
今回の事例は、ファンドから持ち込まれた現実の事例です。制約に集中する全体最適のマネジメントで短期間に数字で結果を出すGoldrattの仕事の仕方が、いかにファンドや短期間に目覚ましい成果を出して企業価値を上げたい経営者と相性がよいかが明らかになりますので、ご期待ください。
ファンドやモノ言う株主の問題に直面している方々はもちろんですが、短期間に、Build-Capitalize-Sustainの3つのステップで
目覚ましい成果を組織にもたらしたい方々には必見のセミナーです。
2年半という短い期間で、企業価値を10倍、利益額をなんと25倍ににまで飛躍させた企業があります。競合他社がコロナ禍の逆風で苦戦する中、これだけの飛躍をどのように実現することができたのでしょうか?
ゴールドラット博士は、企業価値を高める3つのステップを明らかにしています。
- Build ― 圧倒的競争力を構築する
- Capitalize ― お金にする
- Sustain ― 定着させる
今回のTOCクラブでは、こうした成果を生み出したロジックを事例とともに、いかに短期で「逆境からの飛躍」を実現するのか、TOC流の企業価値の上げ方をご紹介します。
「モノ言う株主、ファンド、CFOがなぜTOCの最大の応援者になるのか?」
短期間に目覚ましい成果を出し、企業価値を上げる『ザ・ゴール2』に描かれたストーリーの実践のロジックが現実の事例で明らかになる素晴らしい内容です。
今回の事例は、ファンドから持ち込まれた現実の事例です。制約に集中する全体最適のマネジメントで短期間に数字で結果を出すGoldrattの仕事の仕方が、いかにファンドや短期間に目覚ましい成果を出して企業価値を上げたい経営者と相性がよいかが明らかになりますので、ご期待ください。
ファンドやモノ言う株主の問題に直面している方々はもちろんですが、短期間に、Build-Capitalize-Sustainの3つのステップで
目覚ましい成果を組織にもたらしたい方々には必見のセミナーです。
2022年06月29日【オンライン】
みんなが自然に助け合う仕事の流れの見える化 円谷プロダクション
前年同期比で売上が1.5倍、利益がなんと3.2倍に成長するなど、短期間で飛躍的な成果を出した会社があります。 それが、あの「ウルトラマン」を生んだ円谷プロダクションです。
こうした素晴らしい循環が生まれており、今もなお、取り組みを支えるメンバーの著しい成長が会社の飛躍を支えています。
今回のTOCクラブでは「みんなが自然に助け合う仕事の流れの見える化」と題し、飛躍を遂げる円谷プロダクションに、いま何が起こっているのか、大きな成果の舞台裏にはどんな活動があるのかを円谷プロダクション、経営企画室 小沢典永ゼネラルマネジャーをお招きし、お話しいただきます。
ウルトラマンは、ご存じのように子どもにも大人気ですが、大人も夢中になれる勇気と力が湧いてくるストーリーです。TOCを使って、組織の可能性を引き出す舞台裏のストーリーはまさに勇気と力が湧いてくるストーリーに満ちていて、多くの学びが得られます。
- 複雑な仕事の流れをクリーンに整理し
- 制約を見える化して、自然にみんなが助け合う状況をつくり
- 長年のジレンマをみんなの知恵を引き出し解消する
- そして、問題解決を繰り返す中で人財がどんどん育っていく
こうした素晴らしい循環が生まれており、今もなお、取り組みを支えるメンバーの著しい成長が会社の飛躍を支えています。
今回のTOCクラブでは「みんなが自然に助け合う仕事の流れの見える化」と題し、飛躍を遂げる円谷プロダクションに、いま何が起こっているのか、大きな成果の舞台裏にはどんな活動があるのかを円谷プロダクション、経営企画室 小沢典永ゼネラルマネジャーをお招きし、お話しいただきます。
ウルトラマンは、ご存じのように子どもにも大人気ですが、大人も夢中になれる勇気と力が湧いてくるストーリーです。TOCを使って、組織の可能性を引き出す舞台裏のストーリーはまさに勇気と力が湧いてくるストーリーに満ちていて、多くの学びが得られます。
2022年05月26日【オンライン】
人財育成に集中した投資こそが会社を良くする
「人財育成こそ、最高の投資である」
TOCの取り組みを進めることで多くの方が最も驚かれるのが、”人の成長”です。
ゴールドラット博士が「モチベーションとコラボレーション」に高い価値を見出し、「月曜日が楽しみな会社にしよう」と語ったのも、組織で働く人の変化こそが最も重要であると考えたからでした。
ところが、人財育成にただお金をかけることがすなわち成功をもたらすわけではないのは、みなさんご存知の通りです。
「わざわざ時間を作って研修を受けさせたのに、結局何も変わらなかった」
そんな苦い経験をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、今回のTOCクラブでは「人財育成に集中した投資こそが会社を良くする」と題し、人財育成への投資によって、会社の危機を飛躍に変え、なんと4000%を越えるROIを実現した事例をご紹介します。
今回の事例では、研修を通じてTOCの理論を学び、その内容を実務の問題解決に応用しながら回を進める”実務直結型の実践
研修”に投資した結果、研修期間中から制約に集中した活動がスタートし、短期間で売上向上と人財育成の両方を実現させることに成功されています。
こうしたお話を伺いながら、人財育成を成果に結びつけるためには一体何が必要なのか、みなさんと学んでいければと思います。
TOCの取り組みを進めることで多くの方が最も驚かれるのが、”人の成長”です。
ゴールドラット博士が「モチベーションとコラボレーション」に高い価値を見出し、「月曜日が楽しみな会社にしよう」と語ったのも、組織で働く人の変化こそが最も重要であると考えたからでした。
ところが、人財育成にただお金をかけることがすなわち成功をもたらすわけではないのは、みなさんご存知の通りです。
「わざわざ時間を作って研修を受けさせたのに、結局何も変わらなかった」
そんな苦い経験をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、今回のTOCクラブでは「人財育成に集中した投資こそが会社を良くする」と題し、人財育成への投資によって、会社の危機を飛躍に変え、なんと4000%を越えるROIを実現した事例をご紹介します。
今回の事例では、研修を通じてTOCの理論を学び、その内容を実務の問題解決に応用しながら回を進める”実務直結型の実践
研修”に投資した結果、研修期間中から制約に集中した活動がスタートし、短期間で売上向上と人財育成の両方を実現させることに成功されています。
- 危機のとき、なぜ人財育成への集中投資を決断できたのか?
- 社内をどの様に巻き込んでいったのか?
- 人財投資により、一体何が変わったのか?
- イノベーション先進国イスラエルで生まれたイノベーションプロセス教育で何が生まれたか?
こうしたお話を伺いながら、人財育成を成果に結びつけるためには一体何が必要なのか、みなさんと学んでいければと思います。
2022年03月22日【オンライン】
ウルグアイはどのようにして世界最速レベルのワクチン接種を実現したか?
「5ヶ月間で70%の対象者にワクチンを届ける」
新型コロナウィルスが猛威を振るうなか、世界的に見ても圧倒的なスピードで国民へのワクチン接種を進めることに成功したのが南米のウルグアイです。
日本でのワクチン接種は2021年2月に始まり、接種率が70%を超えたのは同年秋頃であったことと比較すれば、「5ヶ月間で70%」というウルグアイが達成した目標はどれだけ高い“ザ・ゴール”であったかがよくわかります。
そこで、今回のTOCクラブでは、「ウルグアイはどのようにして世界最速レベルのワクチン接種を実現したか?」と題し、ウルグアイを代表するTOCの世界的トップエキスパートであるラウル・ビアンキ氏にお話をいただきます。
ウルグアイでは国内の戦略的なワクチン展開にTOCを活用し、5Focusing Steps、DBR、在庫マネジメント、クリティカルチェーンといった手法を国をあげて実践。その結果、世界平均の3倍を超える圧倒的な速さで国民にワクチンを届けることに成功しました。
サプライチェーンはTOCが理論的な基礎となっているのは世の中に広く知られていますが、その具体的な応用方法と基本的な考え方について学べる内容になっています。
新型コロナウィルスが猛威を振るうなか、世界的に見ても圧倒的なスピードで国民へのワクチン接種を進めることに成功したのが南米のウルグアイです。
日本でのワクチン接種は2021年2月に始まり、接種率が70%を超えたのは同年秋頃であったことと比較すれば、「5ヶ月間で70%」というウルグアイが達成した目標はどれだけ高い“ザ・ゴール”であったかがよくわかります。
そこで、今回のTOCクラブでは、「ウルグアイはどのようにして世界最速レベルのワクチン接種を実現したか?」と題し、ウルグアイを代表するTOCの世界的トップエキスパートであるラウル・ビアンキ氏にお話をいただきます。
ウルグアイでは国内の戦略的なワクチン展開にTOCを活用し、5Focusing Steps、DBR、在庫マネジメント、クリティカルチェーンといった手法を国をあげて実践。その結果、世界平均の3倍を超える圧倒的な速さで国民にワクチンを届けることに成功しました。
サプライチェーンはTOCが理論的な基礎となっているのは世の中に広く知られていますが、その具体的な応用方法と基本的な考え方について学べる内容になっています。
2022年02月22日【オンライン】
特別講演~大規模ソフトウェアにおける人中心の品質マネジメント革新~
今回のテーマは「大規模ソフトウェアにおける人中心の品質マネジメント革新」です。
経済産業省がまとめた「2005年版組み込みソフトウェア産業実態調査」が明らかにした実態です。それからすでに15年以上経った現在、状況は良くなっているのでしょうか?
この期間、ソフトウェア産業が何もしなかったわけではありません。それどころか、この課題に対して様々な試みが行われていますが、問題は解決するどころか、ますます深刻になり、ソフトウェアは産業界のボトルネックになりつつある、または、すでになっていると広く認識されるようになっています。
開発するソフトウェアがますます複雑になり、開発規模が大きくなり、関係するステークホルダーの数も増え、グローバル競争がますます激しくなる産業界では、ソフトウェアプロジェクトのせいで、経営破綻する企業が出始め、問題はさらに深刻になっているのは言うまでもありません。
「的外れのカイゼンは、現場にメリットをもたらすどころか、深刻なダメージを与えている」
全世界で1000万人が読んだ今も色あせない伝説のベストセラー『ザ・ゴール』の著者ゴールドラット博士の言葉です。様々な試みが行われているにもかかわらず、もしも成果が出ていないとしたら、そのカイゼン努力は的外れなモノなのかもしれません。
今回のセミナーでは、2021年5月の日科技連のソフトウェア品質管理研究会における特別講義「ソフトウェア開発の真の制約とは何か?」のフォローアップ講演として、総工数1万人月を超すソフトウェア開発で人の仕事の質向上に集中した目覚ましい品質改善成果を出した開発トップをお招きし、いかにして実現したかのプロセスをご紹介します。内容は以下の通りです。
ソフトウェアに限らず、不確実性の高い仕事における知的生産性と品質を向上させたい方々すべてに参考になる内容です。
- 3割が計画の品質を達成できていない
- 4分の1が開発途中で機能を削減
- 半分以上が納期遅れ
- 半分以上が予算オーバー
- 品質問題の3分の1がソフトウェア起因
経済産業省がまとめた「2005年版組み込みソフトウェア産業実態調査」が明らかにした実態です。それからすでに15年以上経った現在、状況は良くなっているのでしょうか?
この期間、ソフトウェア産業が何もしなかったわけではありません。それどころか、この課題に対して様々な試みが行われていますが、問題は解決するどころか、ますます深刻になり、ソフトウェアは産業界のボトルネックになりつつある、または、すでになっていると広く認識されるようになっています。
開発するソフトウェアがますます複雑になり、開発規模が大きくなり、関係するステークホルダーの数も増え、グローバル競争がますます激しくなる産業界では、ソフトウェアプロジェクトのせいで、経営破綻する企業が出始め、問題はさらに深刻になっているのは言うまでもありません。
「的外れのカイゼンは、現場にメリットをもたらすどころか、深刻なダメージを与えている」
全世界で1000万人が読んだ今も色あせない伝説のベストセラー『ザ・ゴール』の著者ゴールドラット博士の言葉です。様々な試みが行われているにもかかわらず、もしも成果が出ていないとしたら、そのカイゼン努力は的外れなモノなのかもしれません。
今回のセミナーでは、2021年5月の日科技連のソフトウェア品質管理研究会における特別講義「ソフトウェア開発の真の制約とは何か?」のフォローアップ講演として、総工数1万人月を超すソフトウェア開発で人の仕事の質向上に集中した目覚ましい品質改善成果を出した開発トップをお招きし、いかにして実現したかのプロセスをご紹介します。内容は以下の通りです。
- 総工数1万人月を超える大規模ソフトウェア開発の課題
- ソフトウェア開発の真のボトルネックとは?
- 人を中心としたソフトウェアマネジメント革新 4つのツール
- アナログからデジタルへDX(デジタルトランスフォーメーション)のキモ
- 桁外れの品質改善効果
- マネジメントが変わることで得られる社員満足度向上と離職率の低下
- PDCA:PDを重視するか、CAを重視するかー「品質はプロセスで創りこむ」先達からの学び
- 人の仕事の質を向上させる「QM7つの規律」
- 「月曜日が楽しみな会社にしよう!」Happy Monday Project
ソフトウェアに限らず、不確実性の高い仕事における知的生産性と品質を向上させたい方々すべてに参考になる内容です。
2022年02月11日【オンライン】
世界のイノベーション先進国イスラエルの高校生向け起業家教育とは?
いまや"中東のシリコンバレー"とも呼ばれ、ハイテク分野を中心に世界中から多額の投資を一手に集める世界のイノベーション大国イスラエル。
ノーベル賞の受賞者にもユダヤ人が多いことはよく知られることですが、こうした圧倒的な知的功績の背景には、幼い頃から受ける教育に大きな違いがあることは実はあまり知られていません。
実際、ゴールドラット博士がTOCを生み出し、マネジメントの世界にイノベーションを起こした原点には、「お前の人生の目標は何だ?」と問い、人生の目標を自分の頭で徹底的に考えさせる博士の親の教育があったことは有名な話です。
これはあくまで一例ですが、他にもさまざまな点で日本とは異なる、ブレイクスルーの知的習慣を育むイスラエルの教育とは一体どのようなものなのでしょうか?
そこで今回のTOCクラブでは、「世界のイノベーション先進国イスラエルの高校生向け起業家教育とは?」と題し、実際にイスラエル現地で行われた高校生向け起業家教育プログラムの内容をご紹介します。
「起業家のように考えるって、どういうことだろう?」
こうした素朴な問いからはじまるプログラムですが、
など、ブレイクスルーを起こすための頭の使い方について、わかりやすい事例を交えながら丁寧に考えさせる内容になっています。
日本の子どもたちに向けた教育としてはもちろんですが、大人の私たちが見ても非常に多くの学びがある内容です。
ノーベル賞の受賞者にもユダヤ人が多いことはよく知られることですが、こうした圧倒的な知的功績の背景には、幼い頃から受ける教育に大きな違いがあることは実はあまり知られていません。
実際、ゴールドラット博士がTOCを生み出し、マネジメントの世界にイノベーションを起こした原点には、「お前の人生の目標は何だ?」と問い、人生の目標を自分の頭で徹底的に考えさせる博士の親の教育があったことは有名な話です。
これはあくまで一例ですが、他にもさまざまな点で日本とは異なる、ブレイクスルーの知的習慣を育むイスラエルの教育とは一体どのようなものなのでしょうか?
そこで今回のTOCクラブでは、「世界のイノベーション先進国イスラエルの高校生向け起業家教育とは?」と題し、実際にイスラエル現地で行われた高校生向け起業家教育プログラムの内容をご紹介します。
「起業家のように考えるって、どういうことだろう?」
こうした素朴な問いからはじまるプログラムですが、
- イノベーションとはそもそも何なのか?
- どのようにイノベーティブなアイデアを見つけるのか?
- 起業家に求められる考え方とは?
など、ブレイクスルーを起こすための頭の使い方について、わかりやすい事例を交えながら丁寧に考えさせる内容になっています。
日本の子どもたちに向けた教育としてはもちろんですが、大人の私たちが見ても非常に多くの学びがある内容です。
2021年08月31日【オンライン】
『アート思考のものづくり』―「それが目指す理想?」という自問自答の力
|
今回の講演のテーマは、『アート思考のものづくり』―「それが目指す理想?」という自問自答の力です。
これは、自動車業界の世界のトップブランドであるマツダにおいて、最高のクルマを作るために常に問われる重要な問いの一つです。 マツダは、世界最高のエンジン「SKYACTIV-X」を生み出す技術力に加え、2020年ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど、デザインにおいても世界中で高い評価を獲得していることはみなさんご存知のとおりです。 そして、その原動力には、自分たちの目指す理想、「ザ・ゴール」を徹底して自問自答するものづくりへのこだわりがある、と語るのが、今回特別にご講演いただく、大阪大学教授の延岡健太郎先生です。 延岡先生は今さら言うまでもないですが、イノベーション研究の世界の第一人者の一人。大阪大学卒業後、マツダ株式会社にて商品開発本部に務められ、その後マサチューセッツ工科大学にてMBA、Ph.Dを取得。日本に戻られてからは神戸大学教授、一橋大学イノベーション研究センター長を経て、現在は大阪大学経済学研究科にて世界の企業のイノベーションや価値創造について研究されています。 今回のTOCクラブでは、マツダをはじめイノベーションを起こし続ける世界の企業は何が違うのか、どんな理想「ザ・ゴール」を掲げ、どうやって実現しているのか、私たちがイノベーションを起こすためにはどうすれば良いのかについてお話いただきます。 「イノベーションとは、顧客が高くても喜んで買いたいと熱望する価値を、低コストで創造すること」 これは、今年1月に出版された著書『アート思考のものづくり』にある延岡先生の言葉ですが、「それが目指す理想?」と自らの理想を問い続けることがなぜイノベーションにつながるのか、そのロジックを延岡先生と一緒に考えていければと思います。 2021年07月12日【オンライン】
|
▲画像をクリックするとAmazonの詳細に飛びます▲
|
デジタル化失敗の方程式―全体最適のデジタルトランスフォーメーションプロセス
今回のテーマは、デジタル化失敗の方程式―全体最適のデジタルトランスフォーメーションプロセスです。
「『デジタル化(DX)で画期的な成果を生み出した』という事例を あまり耳にしないのはなぜか?」
いまや世界中のあらゆる組織が避けて通ることのできないデジタル化。
日本では「デジタル庁」創設が決定するなどまさに国を挙げての一大テーマとして議論・実践が進んでいますが、デジタルの導入で部分的な効率を改善しても、全体のパフォーマンスが向上するとは限らないどころか、むしろ本質的な問題解決から遠ざかってしまいかねないのはみなさんご存知の通りです。
そこには「効率的なデジタルツールさえ導入すれば、生産性が上がり、重要な問題が解決するはず」という思い込みがないでしょうか?
デジタル化について、ゴールドラット博士は『チェンジ・ザ・ルール!』で
"Necessary, but not sufficient."(必要だが十分ではない)
と語っており、デジタル化の変革を成功させるための重要な前提となるロジックを紹介しています。
そこで、今回のTOCクラブでは
について、民間・行政の両方の成果事例を織り交ぜながらご紹介します。
本質的な問題解決に取り組み、デジタル化で目覚ましい成果を出すプロセス、いわば「デジタル化成功の方程式」とも言える考え方を、事例から一緒に学んでいければと思います。
「『デジタル化(DX)で画期的な成果を生み出した』という事例を あまり耳にしないのはなぜか?」
いまや世界中のあらゆる組織が避けて通ることのできないデジタル化。
日本では「デジタル庁」創設が決定するなどまさに国を挙げての一大テーマとして議論・実践が進んでいますが、デジタルの導入で部分的な効率を改善しても、全体のパフォーマンスが向上するとは限らないどころか、むしろ本質的な問題解決から遠ざかってしまいかねないのはみなさんご存知の通りです。
そこには「効率的なデジタルツールさえ導入すれば、生産性が上がり、重要な問題が解決するはず」という思い込みがないでしょうか?
デジタル化について、ゴールドラット博士は『チェンジ・ザ・ルール!』で
"Necessary, but not sufficient."(必要だが十分ではない)
と語っており、デジタル化の変革を成功させるための重要な前提となるロジックを紹介しています。
そこで、今回のTOCクラブでは
- 「デジタル化失敗の方程式」とは?
- 全体最適の取り組みでデジタル化に成功した事例
- 「デジタル化失敗の方程式」を避け、目覚ましい成果がでるプロセス
について、民間・行政の両方の成果事例を織り交ぜながらご紹介します。
本質的な問題解決に取り組み、デジタル化で目覚ましい成果を出すプロセス、いわば「デジタル化成功の方程式」とも言える考え方を、事例から一緒に学んでいければと思います。
2021年06月23日【オンライン】
東国原 元宮崎県知事が語る「逆境からの飛躍」
前任の知事と県幹部が談合問題で逮捕されるという前代未聞のスキャンダルの中でスタートした、東国原知事の宮崎県改革。
その矢先、口蹄疫と鳥インフルエンザが発生。その渦中、県の経済を支える主要産業である農畜産物が壊滅的なダメージを
受けるのを避け、いち早く、安心・安全を確保し、宮崎ブランドを逆境の中でさらに高めて「経済と安全の両立」を素早く実現したことは、まだ多くの方々が覚えているのではないかと思います。
当時、ゴールドラットジャパンCEOの岸良裕司氏は、東国原知事が取り組んでいた「新みやざき創造戦略」に県外の有識者という
位置づけで参画し、県の行政職員と共に、渦中にいたこともあり、その一連の現場の活動をつぶさに見てきました。
東国原知事は「新みやざき創造戦略」を県職員と策定、「県民総力戦」と訴え、県民を巻き込み、改革の工程表を作成し、変革を加速していきました。特にユニークなのは、いくら予算をつけたかではなく、結果を出せたかどうかという結果主義で評価するというマネジメントを導入した点です。
この事例は、米国で開催された国際コンファレンスでも公開されましたがTOCを活用した包括的な行政マネジメントの世界の先駆けとなる取り組みとして高い評価を得て、多くの行政関係者に影響を与えたといわれています。
その一つの事例がユタ州の財務長官であるクリスティン・コックスさんです。目が不自由ながら米国でベストの行政改革アワードを取られた方です。
その矢先、口蹄疫と鳥インフルエンザが発生。その渦中、県の経済を支える主要産業である農畜産物が壊滅的なダメージを
受けるのを避け、いち早く、安心・安全を確保し、宮崎ブランドを逆境の中でさらに高めて「経済と安全の両立」を素早く実現したことは、まだ多くの方々が覚えているのではないかと思います。
当時、ゴールドラットジャパンCEOの岸良裕司氏は、東国原知事が取り組んでいた「新みやざき創造戦略」に県外の有識者という
位置づけで参画し、県の行政職員と共に、渦中にいたこともあり、その一連の現場の活動をつぶさに見てきました。
東国原知事は「新みやざき創造戦略」を県職員と策定、「県民総力戦」と訴え、県民を巻き込み、改革の工程表を作成し、変革を加速していきました。特にユニークなのは、いくら予算をつけたかではなく、結果を出せたかどうかという結果主義で評価するというマネジメントを導入した点です。
この事例は、米国で開催された国際コンファレンスでも公開されましたがTOCを活用した包括的な行政マネジメントの世界の先駆けとなる取り組みとして高い評価を得て、多くの行政関係者に影響を与えたといわれています。
その一つの事例がユタ州の財務長官であるクリスティン・コックスさんです。目が不自由ながら米国でベストの行政改革アワードを取られた方です。
現在、新型コロナウィルスで大変なことになっていますが、国難ともいえる危機の中だからこそ、口蹄疫や鳥インフルエンザの修羅場の中で東国原知事をはじめ県の行政職員がとった当時の一連の行動から学ぶことは多いのではなかと思います。
普段のテレビではお目にかかれない、現場をやる気にさせる東国原元知事の行政マネジメント手腕から学ぶとともに「逆境から飛躍する」ヒントが得られるはず。私どもも本当に楽しみです。
普段のテレビではお目にかかれない、現場をやる気にさせる東国原元知事の行政マネジメント手腕から学ぶとともに「逆境から飛躍する」ヒントが得られるはず。私どもも本当に楽しみです。
2020年10月20日【オンライン】
イノベーション現場の飛躍的生産性向上は可能か?
イノベーションは一部の天才にしかできないものでしょうか?
ますます技術が複雑になり、一人の天才だけでイノベーションが起こせることがますます難しくなっているのは、世の中で広く認知されつつあります。
世の中で今までやったことがないことをするのがイノベーション。それを実現するためのイノベーション現場は、多くの技術的
チャレンジをしなければなりません。しかも、その現場には多くの人が関わります。
今までやったことがないことにチャレンジするのですから、生産性を上げるところか、議論することさえ難しいと一般に思われていますが、本当でしょうか?
マツダのシニアイノベーションフェロー 人見氏が現場に問いかけた質問です。
今回のTOCクラブでは、世界的にも有名なマツダのMBD(Model Based Development)の現場でいかにTOCが活用されているかを、実際に現場で目覚ましい成果を出しているご本人にお話をしていただきます。
イノベーション現場のど真ん中にいる技術者だからこそ話せる生々しい現実と、それを解消するシンプルなソリューションをご紹介します。
飛躍的生産性アップのおかげで、あっという間に残業激減。趣味の時間もでき、ワークライフバランスも結果的に実現し、さらには世界一のイノベーションと認められるグローバルアワードを受賞した事例で、話を聞いているだけでワクワク、でも、そこには現場で実践できる知恵の数々が満載の素晴らしい内容です。ぜひご期待ください。
ますます技術が複雑になり、一人の天才だけでイノベーションが起こせることがますます難しくなっているのは、世の中で広く認知されつつあります。
世の中で今までやったことがないことをするのがイノベーション。それを実現するためのイノベーション現場は、多くの技術的
チャレンジをしなければなりません。しかも、その現場には多くの人が関わります。
今までやったことがないことにチャレンジするのですから、生産性を上げるところか、議論することさえ難しいと一般に思われていますが、本当でしょうか?
- 皆さんのチームメンバーが今日何の仕事をするか知っていますか?
- いくつタスクを抱えているか知っていますか?
- 各タスクは何をインプットにして仕事を始めていますか?
- 本当に今始めるべき条件はそろっていますか?
- 優先度は担当者に任せきりではありませんか?
- 全員が均等に忙しいですか?
- 特定の人に仕事が集中していませんか?
- その人で組織のパフォーマンスが決まっていませんか?
- その人にその人でなくてもいい仕事までさせていませんか?
マツダのシニアイノベーションフェロー 人見氏が現場に問いかけた質問です。
今回のTOCクラブでは、世界的にも有名なマツダのMBD(Model Based Development)の現場でいかにTOCが活用されているかを、実際に現場で目覚ましい成果を出しているご本人にお話をしていただきます。
イノベーション現場のど真ん中にいる技術者だからこそ話せる生々しい現実と、それを解消するシンプルなソリューションをご紹介します。
飛躍的生産性アップのおかげで、あっという間に残業激減。趣味の時間もでき、ワークライフバランスも結果的に実現し、さらには世界一のイノベーションと認められるグローバルアワードを受賞した事例で、話を聞いているだけでワクワク、でも、そこには現場で実践できる知恵の数々が満載の素晴らしい内容です。ぜひご期待ください。
2020年08月31日【オンライン】
ソフトウェア品質崩壊はどこから来るのか?
今回のテーマは、「ソフトウェア品質崩壊はどこから来るのか」です。
経済産業省がまとめた「2005年版組み込みソフトウェア産業実態調査」が明らかにした実態です。それからすでに15年以上経った現在、状況は良くなっているのでしょうか?
この期間、ソフトウェア産業が何もしなかったわけではありません。それどころか、この課題に対して様々な試みが行われていますが、問題は解決するどころか、ますます深刻になり、ソフトウェアは産業界のボトルネックになりつつある、または、既になっていると産業界で広く認識されるようになっています。
開発するソフトウェアがますます複雑になり、開発規模が大きくなり、関係するステークホルダーの数も増え、競争がますます激しくなる産業界では、ソフトウェアプロジェクトのせいで、経営破綻する企業が出始め、問題はさらに深刻になっているのは言うまでもありません。
「的外れのカイゼンは、現場にメリットをもたらすどころか、深刻なダメージを与えている」
ゴールドラット博士の言葉です。様々な試みが行われているにもかかわらず、もしも成果が出ていないとしたら、そのカイゼン努力はすべて的外れなモノなのかもしれません。
今回のTOCクラブでは、ソフトウェア開発の真の制約とは何かを明らかにし、そこに取り組むことで、目覚ましい成果を出すシンプルなロジックと事例をご紹介します。
TOCらしい、AHA! (その手があったか!)というソリューションです、ご期待ください。
特別な準備は必要ありません。組織を良くしたい。プロジェクトを良くしたいという思いだけお持ちいただければ十分です。
今回の内容は、ソフトウェアに限らず、不確実性の高いプロジェクトすべてに適用できます。日常の仕事はもちろん、数か国をまたがるような大規模プロジェクトでも適用可能、もちろんテレワークでも目覚しい成果を短期間でもたらします。
- 3割が計画の品質を達成できない
- 4分の1が開発途中で機能を削減
- 半分以上が納期遅れ
- 半分以上が予算オーバー
- 品質問題の3分の1がソフトウェア起因
経済産業省がまとめた「2005年版組み込みソフトウェア産業実態調査」が明らかにした実態です。それからすでに15年以上経った現在、状況は良くなっているのでしょうか?
この期間、ソフトウェア産業が何もしなかったわけではありません。それどころか、この課題に対して様々な試みが行われていますが、問題は解決するどころか、ますます深刻になり、ソフトウェアは産業界のボトルネックになりつつある、または、既になっていると産業界で広く認識されるようになっています。
開発するソフトウェアがますます複雑になり、開発規模が大きくなり、関係するステークホルダーの数も増え、競争がますます激しくなる産業界では、ソフトウェアプロジェクトのせいで、経営破綻する企業が出始め、問題はさらに深刻になっているのは言うまでもありません。
「的外れのカイゼンは、現場にメリットをもたらすどころか、深刻なダメージを与えている」
ゴールドラット博士の言葉です。様々な試みが行われているにもかかわらず、もしも成果が出ていないとしたら、そのカイゼン努力はすべて的外れなモノなのかもしれません。
今回のTOCクラブでは、ソフトウェア開発の真の制約とは何かを明らかにし、そこに取り組むことで、目覚ましい成果を出すシンプルなロジックと事例をご紹介します。
TOCらしい、AHA! (その手があったか!)というソリューションです、ご期待ください。
特別な準備は必要ありません。組織を良くしたい。プロジェクトを良くしたいという思いだけお持ちいただければ十分です。
今回の内容は、ソフトウェアに限らず、不確実性の高いプロジェクトすべてに適用できます。日常の仕事はもちろん、数か国をまたがるような大規模プロジェクトでも適用可能、もちろんテレワークでも目覚しい成果を短期間でもたらします。
2020年08月19日【オンライン】
不確実性の高い環境において「トヨタ生産方式」で目覚ましい成果を出すためには
「世界で称賛され、世界の工場を変えたと言われるトヨタ生産方式が、日本の産業界において2割も使われていないのはなぜなのか?」
『トヨタ生産方式』の著者、大野耐一氏をマイヒーローと世界中で公言していたゴールドラット博士が長年にわたって思っていた疑問です。
不確実性のある環境にはトヨタ生産方式の適用は難しいと一般的に思われがちですが、極めて高い不確実性が伴う環境においても、
トヨタ生産方式で目覚ましい成果を出すことが可能であることは、昨年TOCクラブで毎回満員御礼で、追加公演を何度も行い、大きな話題となったトヨタ自動車元技監の林南八氏の講演の中で事例と共に明らかになっているのはご存知の通りです。
林南八氏は「トヨタ生産方式」は誤解されていると主張し、手法ではなく、その本質を理解することが大事と語っています。
今回のTOCクラブでは、「トヨタ生産方式を理論化しなさい」と大野耐一氏に宿題をもらったゴールドラット博士が、どうこの宿題に
取り組んだのかをたどることで、不確実性の高い現場においても「トヨタ生産方式の本質」を科学的に理論化し、手法がもつ「境界条件」を理解すれば、導入の失敗を避けることができるだけではなく、目覚ましい成果を出せることを、シンプルにわかりやすく、実践的に、目覚ましい成果とともにご紹介します。
『トヨタ生産方式』の著者、大野耐一氏をマイヒーローと世界中で公言していたゴールドラット博士が長年にわたって思っていた疑問です。
不確実性のある環境にはトヨタ生産方式の適用は難しいと一般的に思われがちですが、極めて高い不確実性が伴う環境においても、
トヨタ生産方式で目覚ましい成果を出すことが可能であることは、昨年TOCクラブで毎回満員御礼で、追加公演を何度も行い、大きな話題となったトヨタ自動車元技監の林南八氏の講演の中で事例と共に明らかになっているのはご存知の通りです。
林南八氏は「トヨタ生産方式」は誤解されていると主張し、手法ではなく、その本質を理解することが大事と語っています。
今回のTOCクラブでは、「トヨタ生産方式を理論化しなさい」と大野耐一氏に宿題をもらったゴールドラット博士が、どうこの宿題に
取り組んだのかをたどることで、不確実性の高い現場においても「トヨタ生産方式の本質」を科学的に理論化し、手法がもつ「境界条件」を理解すれば、導入の失敗を避けることができるだけではなく、目覚ましい成果を出せることを、シンプルにわかりやすく、実践的に、目覚ましい成果とともにご紹介します。
2020年07月01日【オンライン】
マツダ金井元会長が語るバックキャストイノベーション
今回はなんとマツダの元会長(現相談役)である金井氏をお招きして、苦境から飛躍的成長を遂げたマツダの逆境から飛躍への道のりについて講演をしていただきます。
経営危機の修羅場の中、組織の存続さえ危ぶまれる中、飛躍の道を描くことは可能でしょうか?
組織の変革が進まない時に良く言われるのは、「危機感がない」ということですが、「危機感」がありさえすれば改革は進むのでしょうか?
危機感を動機とした改革は決して長続きしないのは論理的に明らかです。なぜならば、危機が去ってしまえば改革の動機がなくなってしまうからです。
4期連続の赤字。自らの生き残りさえ危ぶまれる経営危機の中、広島・山口の地元雇用に大きな責任をもつマツダが選んだのは、生き残りではなく飛躍への道。現在は、目覚ましい成果で世の中の注目を集めるマツダですが、その飛躍の道は、この逆境の中で始まりました。
「TOCは一言でいうと集中である」というゴールドラット博士の言葉通り、今はやらないという逆転の発想と集中で、業界の常識を打ち破るイノベーションをもたらし、苦境から飛躍的成長を遂げたマツダの逆境から飛躍への道のりを紹介します。
逆境こそ飛躍のチャンス。聞いているだけで勇気がモリモリ、やる気がワクワク湧いてくる本当に素晴らしい講演です。
『マツダ 心を燃やす逆転の経営』でベストセラーとなっているマツダの金井元会長(現相談役)のお話を聞くまたとないチャンスです。
経営危機の修羅場の中、組織の存続さえ危ぶまれる中、飛躍の道を描くことは可能でしょうか?
組織の変革が進まない時に良く言われるのは、「危機感がない」ということですが、「危機感」がありさえすれば改革は進むのでしょうか?
危機感を動機とした改革は決して長続きしないのは論理的に明らかです。なぜならば、危機が去ってしまえば改革の動機がなくなってしまうからです。
4期連続の赤字。自らの生き残りさえ危ぶまれる経営危機の中、広島・山口の地元雇用に大きな責任をもつマツダが選んだのは、生き残りではなく飛躍への道。現在は、目覚ましい成果で世の中の注目を集めるマツダですが、その飛躍の道は、この逆境の中で始まりました。
「TOCは一言でいうと集中である」というゴールドラット博士の言葉通り、今はやらないという逆転の発想と集中で、業界の常識を打ち破るイノベーションをもたらし、苦境から飛躍的成長を遂げたマツダの逆境から飛躍への道のりを紹介します。
- マツダの紹介
- 地場雇用支える広島・山口の企業としての社会的責任
- 倒産寸前の苦境の中、エンジニアたちが描いた志
- 振り切って未来を考え、一つひとつ実現するバックキャストイノベーション
- ロマンとソロバン
- 本当の成果は人が育ったこと
- さらなる飛躍へ
逆境こそ飛躍のチャンス。聞いているだけで勇気がモリモリ、やる気がワクワク湧いてくる本当に素晴らしい講演です。
『マツダ 心を燃やす逆転の経営』でベストセラーとなっているマツダの金井元会長(現相談役)のお話を聞くまたとないチャンスです。
2019年08月07日【京都】
2019年09月04日【広島】
2019年09月26日【東京】
2019年11月18日【東京】
2019年12月05日【名古屋】
2020年01月15日【名古屋】
2019年09月04日【広島】
2019年09月26日【東京】
2019年11月18日【東京】
2019年12月05日【名古屋】
2020年01月15日【名古屋】
イノベーションの制約とはなんでしょうか?
「イノベーションの制約とはなんでしょうか?」
あらゆる仕事には流れがあるように、イノベーションも発想から、事業化までの道のりがありますが、その流れは良いでしょうか? 悪いでしょうか?
イノベーションは茨の道のようだとも良く語られますが、本当にそうでしょうか? その茨の道には以下のようなトリが生息していることがだんだん明らかになってきています。
そういうトリたちでさえ、次々と味方につけて、イノベーションを加速できるならば、世の中がWOW!というイノベーションを信じられないほどの短期間で実現することも可能ではないかと・・・
「現代のイノベーションはたった一人の天才でできるほど甘いものではない」とは良く言われるところですが、だからこそ、一人ではなく、周囲を巻き込み大きな流れにしていくプロセスこそ大事ではないでしょうか?
おかげさまでベストセラーとなった『優れた発想はなぜゴミ箱に捨てられるのか?』(ダイヤモンド社)の中の事例では、プロセスさえあれば、多くのステークホルダーを巻き込み、わずか数日でイノベーションを実現することも可能であることが示されています。
我々は信じていることがあります。それは
「プロセスさえあれば、誰でも世界を変えるイノベーターになれる」
ということです。今回のTOCクラブでは、ステークホルダーのすべてがWin-WinでつながるTOC流イノベーションプロセスについて紹介します。
企業、研究所で、イノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
あらゆる仕事には流れがあるように、イノベーションも発想から、事業化までの道のりがありますが、その流れは良いでしょうか? 悪いでしょうか?
- 滞留どころじゃない、手戻りだらけ
- 決まったか、決まってないかさえわからない
- 審査される度に宿題ばっかりが増える
イノベーションは茨の道のようだとも良く語られますが、本当にそうでしょうか? その茨の道には以下のようなトリが生息していることがだんだん明らかになってきています。
- いちいち確認ばかりしたがる「確認トリ」
- 確認トリの周囲に群れる「ご機嫌トリ」
- そういう流れに巻き込まれない八方美人の「風見トリ」
そういうトリたちでさえ、次々と味方につけて、イノベーションを加速できるならば、世の中がWOW!というイノベーションを信じられないほどの短期間で実現することも可能ではないかと・・・
「現代のイノベーションはたった一人の天才でできるほど甘いものではない」とは良く言われるところですが、だからこそ、一人ではなく、周囲を巻き込み大きな流れにしていくプロセスこそ大事ではないでしょうか?
おかげさまでベストセラーとなった『優れた発想はなぜゴミ箱に捨てられるのか?』(ダイヤモンド社)の中の事例では、プロセスさえあれば、多くのステークホルダーを巻き込み、わずか数日でイノベーションを実現することも可能であることが示されています。
我々は信じていることがあります。それは
「プロセスさえあれば、誰でも世界を変えるイノベーターになれる」
ということです。今回のTOCクラブでは、ステークホルダーのすべてがWin-WinでつながるTOC流イノベーションプロセスについて紹介します。
企業、研究所で、イノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
2019年06月13日【東京】
2019年07月10日【京都】
2019年07月10日【京都】
優れた発想はなぜ、ゴミ箱に捨てられてしまうのか?
「すごいアイデアなのになぜ通らないんだろう?」
実際、多くの優れた発想は会社のゴミ箱に捨てられてないでしょうか?その発想が優れていればいるほど、その可能性は高くなるのかもしれません。
なぜならば、今までに世の中にない新しい発想であればあるほど、従来の考え方しか知らない人たちがその価値を正しく評価するのは難しくなると言えるからです。
優れた発想だけで世の中を変えるイノベーションが実現できるほど甘いものではないことは、実務家ならば誰でも痛いほどわかっているはず。優れた発想が世の中にイノベーションを引き起こすまでの道のりには、次のような過程があります。
イノベーションを実現し世に問う前に、それを評価するのは、一般に経営幹部の方々。つまり、様々な社内の関門を突破せずして、イノベーションを世に問うことはできないと言えます 。
多くの経営幹部の方々は、優れた成功体験を過去に持っています。でも、その過去の考え方をベースに、未来を創り出すイノベーションを本当に評価できるのでしょうか?
「コストはどのくらいかかるのか?!」
「市場規模は?!」
「競合相手はどうなのか?!」
「投資対効果は?!」
「いったい誰が買うんだ?!」
いかに優れたアイデアであっても、イノベーションを起こす過程で、これらのような「ありがたいご指導」をいただくことは少なくなく、このような「ありがたいご指導」をいただくたびに、もともとの尖った発想は、再三の修正を余儀なくされ、元の尖りを失い、結果的に誰にも刺さらないアイデアに丸まってしまいガチになります。
世の中がますます複雑になってくるにつれ、一人の天才イノベーターが様々な困難を乗り越え、イノベーションを引き起こせるほど甘い世の中ではもはやないとも言われる昨今、多くのステークホルダーを巻き込み、イノベーションを起こすことが必要になってきています。
我々は信じていることがあります。それは、
「プロセスさえあれば、誰でも世界を変えるイノベーターになれる」
ということです。今回のTOCクラブでは、すべてのステークホルダーがWin-WinでつながるTOC流イノベーションプロセスについて紹介します。
企業、研究所で、イノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
実際、多くの優れた発想は会社のゴミ箱に捨てられてないでしょうか?その発想が優れていればいるほど、その可能性は高くなるのかもしれません。
なぜならば、今までに世の中にない新しい発想であればあるほど、従来の考え方しか知らない人たちがその価値を正しく評価するのは難しくなると言えるからです。
優れた発想だけで世の中を変えるイノベーションが実現できるほど甘いものではないことは、実務家ならば誰でも痛いほどわかっているはず。優れた発想が世の中にイノベーションを引き起こすまでの道のりには、次のような過程があります。
- アイデアを発想する
- アイデアを形にまとめる
- ビジネス案をまとめる
- 企画を通す
- 開発する
- 販売する
- 事業を拡大し世の中にイノベーションを起こす
イノベーションを実現し世に問う前に、それを評価するのは、一般に経営幹部の方々。つまり、様々な社内の関門を突破せずして、イノベーションを世に問うことはできないと言えます 。
多くの経営幹部の方々は、優れた成功体験を過去に持っています。でも、その過去の考え方をベースに、未来を創り出すイノベーションを本当に評価できるのでしょうか?
「コストはどのくらいかかるのか?!」
「市場規模は?!」
「競合相手はどうなのか?!」
「投資対効果は?!」
「いったい誰が買うんだ?!」
いかに優れたアイデアであっても、イノベーションを起こす過程で、これらのような「ありがたいご指導」をいただくことは少なくなく、このような「ありがたいご指導」をいただくたびに、もともとの尖った発想は、再三の修正を余儀なくされ、元の尖りを失い、結果的に誰にも刺さらないアイデアに丸まってしまいガチになります。
世の中がますます複雑になってくるにつれ、一人の天才イノベーターが様々な困難を乗り越え、イノベーションを引き起こせるほど甘い世の中ではもはやないとも言われる昨今、多くのステークホルダーを巻き込み、イノベーションを起こすことが必要になってきています。
我々は信じていることがあります。それは、
「プロセスさえあれば、誰でも世界を変えるイノベーターになれる」
ということです。今回のTOCクラブでは、すべてのステークホルダーがWin-WinでつながるTOC流イノベーションプロセスについて紹介します。
企業、研究所で、イノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
2018年12月21日【京都】
2019年01月22日【東京】
2019年01月30日【名古屋】
2019年02月20日【広島】
2019年01月22日【東京】
2019年01月30日【名古屋】
2019年02月20日【広島】
お客様にWOW!と言わせる「市場の教育」
「いい商品なのになぜ売れないんだろう?」
一部のお客様には熱狂的に支持されている。でも、なぜかそれが広く認識されず、売り上げは伸び悩み、事業としてなりたたなくなってしまう。そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか?
「優れた商品であっても、それだけでは売れない。市場の教育が必要なのだ」 ゴールドラット博士の言葉です。
イノベーションとは今までに世の中にない新しい商品やサービスを生み出すことです。
世の中に今まで存在していないのだから、その価値を市場に伝えるために、「市場の教育」が欠かせないのは言うまでもないことです。
今回のTOCクラブでは「市場の教育」をテーマにメーカー、取引先、販売店、消費者が複雑に絡む市場構造の中で、すべてのステークホルダーにWOW!と言わせる価値を構築し、「市場の教育」を行い、事業をいかに構築していくかを議論していきます。
さらに、すべてのステークホルダーにWOW!と言われるスゴイ商品も実際にご紹介し、実際にイノベーションに関わった本人にもプレゼンをしていただきますのでどうぞお楽しみに!
企業、研究所で、イノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
一部のお客様には熱狂的に支持されている。でも、なぜかそれが広く認識されず、売り上げは伸び悩み、事業としてなりたたなくなってしまう。そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか?
「優れた商品であっても、それだけでは売れない。市場の教育が必要なのだ」 ゴールドラット博士の言葉です。
イノベーションとは今までに世の中にない新しい商品やサービスを生み出すことです。
世の中に今まで存在していないのだから、その価値を市場に伝えるために、「市場の教育」が欠かせないのは言うまでもないことです。
今回のTOCクラブでは「市場の教育」をテーマにメーカー、取引先、販売店、消費者が複雑に絡む市場構造の中で、すべてのステークホルダーにWOW!と言わせる価値を構築し、「市場の教育」を行い、事業をいかに構築していくかを議論していきます。
さらに、すべてのステークホルダーにWOW!と言われるスゴイ商品も実際にご紹介し、実際にイノベーションに関わった本人にもプレゼンをしていただきますのでどうぞお楽しみに!
企業、研究所で、イノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
2018年11月20日【広島】
2018年11月21日【京都】
2018年11月22日【名古屋】
2018年11月26日【東京】
2018年11月21日【京都】
2018年11月22日【名古屋】
2018年11月26日【東京】
日本が世界をリードするイノベーション大国になれる理由ーイノベーション先進国イスラエルから見た日本の可能性
「なぜ、イスラエルは、イノベーションを次々と生み出すのか?」
ユダヤ人が世界に占める人口は1000万人以下なのに、次々とノーベル賞学者を生み出し、さらに、様々なイノベーションを世の中に生み出しているのはご存知の通りです。
今回、イスラエルの政府機関、産業界の様々な分野で要職を務め、イノベーションを起こしてきたVIP、Eli Abramov博士が、先月
来日した際にお話いただいた特別講演の内容をビデオでご覧いただきながら、それに岸良が解説を加えるというちょっと贅沢な内容です。
Eli Abramov博士
イスラエルの研究機関の最高峰 ネゲブ原子力研究センターの元チーフオペレーションオフィサー、その後、イスラエル最大のエンジニアリング会社Baran GroupのCEOなど民間企業の要職も務め、イノベーションのみならず、プロジェクトマネジメントやサプライチェーンでTOCを駆使し目覚ましい成果をだすTOCのトップエキスパートです。
Abramov博士の経歴の凄さはもちろんですが、いかに彼がVIPであるかというと、TOCの国際大会でゴールドラット博士と会う際に、常にSPが周囲に張りいていたというくらい、イスラエルのイノベーションをリードするVIPです。
Abramov博士のセミナーの内容は以下の通りとなります。
ご存知の通り、TOCはブレークスルー思考そのものです。現在の延長線上にはない解決策で、新しい未来を創ります。
それをイノベーションに活用すると、日本でどんなことが起きるのかをお話をしていただきます。
企業、研究所でイノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、行政マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
ユダヤ人が世界に占める人口は1000万人以下なのに、次々とノーベル賞学者を生み出し、さらに、様々なイノベーションを世の中に生み出しているのはご存知の通りです。
今回、イスラエルの政府機関、産業界の様々な分野で要職を務め、イノベーションを起こしてきたVIP、Eli Abramov博士が、先月
来日した際にお話いただいた特別講演の内容をビデオでご覧いただきながら、それに岸良が解説を加えるというちょっと贅沢な内容です。
Eli Abramov博士
イスラエルの研究機関の最高峰 ネゲブ原子力研究センターの元チーフオペレーションオフィサー、その後、イスラエル最大のエンジニアリング会社Baran GroupのCEOなど民間企業の要職も務め、イノベーションのみならず、プロジェクトマネジメントやサプライチェーンでTOCを駆使し目覚ましい成果をだすTOCのトップエキスパートです。
Abramov博士の経歴の凄さはもちろんですが、いかに彼がVIPであるかというと、TOCの国際大会でゴールドラット博士と会う際に、常にSPが周囲に張りいていたというくらい、イスラエルのイノベーションをリードするVIPです。
Abramov博士のセミナーの内容は以下の通りとなります。
- イスラエルがイノベーション先進国である理由
- イスラエルから見た日本
- 日本がイスラエルに勝るとも劣らないイノベーション大国になれる理由
- イノベーション大国にむけて
ご存知の通り、TOCはブレークスルー思考そのものです。現在の延長線上にはない解決策で、新しい未来を創ります。
それをイノベーションに活用すると、日本でどんなことが起きるのかをお話をしていただきます。
企業、研究所でイノベーションを進めている方々のみならず、組織運営、行政マネジメントなどで、既成概念を打破するイノベーションを起こしたい人、必須のセミナーです。
2018年09月03日【東京】
2018年09月05日【広島】
2018年09月06日【名古屋】
2018年10月31日【京都】
2018年09月05日【広島】
2018年09月06日【名古屋】
2018年10月31日【京都】
プロセスさえあれば誰でも世界を変えるイノベーターになれる
「日本のあらゆる企業がイノベーションを謳っている。でも、イノベーティブだと思える日本企業はほとんどない。一体どうなっているんでしょうか?」
ある有名ビジネス雑誌の友人から、最近相談された質問です。
AIやIoTなど様々な技術が導入されるなか、技術の進化はさらに加速しています。でもその技術は本当にユーザーに価値をもたらしているのでしょか? むしろ、ユーザーに混乱さえもたらしているケースも少なくないのかもしれません。
ユーザーに価値をもたらしていないならば、イノベーションなど起こせるはずはないかと・・・
イノベーションは大事。でも、どうやってイノベーションを引き起こすのかそれが産業界の大きな課題になっているのは言うまでもありません。
もちろん、様々な試みも始まっています。
いずれも目覚ましい成功につながっている事例は乏しいのが現状なのかもしれません。
「イノベーションは本当に一部の天才の人にしかできないものなのでしょうか?」
あらゆる産業界で目覚ましいブレークスルーを引き起こしてきているTOCですが、そこには、イノベーションを引き起こすプロセスが存在します。その知識体系をまとめたものがTOC for Innovationです。
実は、このイノベーションですが今まであらゆる産業界で実践され、目覚ましい成果をあげてきましたが、あまりにパワフルな手法で、極めて特許性の高いInnovationの発想が次々と出るために、一般公開するワークショップをすることが難しく、ゴールドラットグループの顧客向けにのみ、クローズな環境で開催されてきました。今回のTOCクラブでは、このプロセスを紹介します。
TOC for Innovationのプロセスはシンプルに、以下の質問から始めます。
「クライアントにとって、極めて重大な要望、しかも競合が簡単にマネできない要望とは何か?」
この問いに答えるために、次のプロセスで新たな発想を導きだします。
すべてのプロセスが、革新的な発想を導きだすとともに、それをさらに尖らせることが可能。WOW!と言われる商品の企画を磨き上げるプロセスです。
私自身もハイテクの技術企画、商品企画をやってきたマーケターでした。
一般に、企業の企画プロセスは、さまざまなゲート(関門)があり、それが企画の質を高め、事業化するために活用されていますが、本当に役に立っているのでしょうか?
こういった企画プロセスでありがちな議論は、基本的には企画をより練り上げるためのものだと思って行われるものですが、実際には、現場のモチベーションを下げてしまったり、とにかく企画を通すために、コスト検討ばっかりに終始してしまい、当初の企画のエッジが削がれてしまい、ユーザーの心に刺さらない企画に落ち着いてしまうことも少なくありません。
TOC for Innovationで変えるのは、企画のマネジメントプロセスそのものです。尖った発想を、磨き上げ、鍛え上げることで、世の中にない価値をもたらすイノベーションを実現するため、経営陣もフルサポートできる環境を作っていきます。しかも、組織の未来を支える「商品で語る中期経営計画」までできてしまいます。
新しい発想をいかに創り、鍛え上げるか、その手があったか!と思えるTOCらしい、シンプルなプロセス。きっとワクワクしていただけるものと思います。
「プロセスさえあれば誰でも世界を変えるイノベーターなれる」
そう信じられる知識体系をご紹介したいと思っています。
ある有名ビジネス雑誌の友人から、最近相談された質問です。
AIやIoTなど様々な技術が導入されるなか、技術の進化はさらに加速しています。でもその技術は本当にユーザーに価値をもたらしているのでしょか? むしろ、ユーザーに混乱さえもたらしているケースも少なくないのかもしれません。
ユーザーに価値をもたらしていないならば、イノベーションなど起こせるはずはないかと・・・
イノベーションは大事。でも、どうやってイノベーションを引き起こすのかそれが産業界の大きな課題になっているのは言うまでもありません。
もちろん、様々な試みも始まっています。
- 高額な報酬で、海外の有名なトップサイエンティストを招く
- 海外のイノベーティブな企業を買収または提携する
- イノベーションセンターなどの部署や施設を創る
いずれも目覚ましい成功につながっている事例は乏しいのが現状なのかもしれません。
「イノベーションは本当に一部の天才の人にしかできないものなのでしょうか?」
あらゆる産業界で目覚ましいブレークスルーを引き起こしてきているTOCですが、そこには、イノベーションを引き起こすプロセスが存在します。その知識体系をまとめたものがTOC for Innovationです。
実は、このイノベーションですが今まであらゆる産業界で実践され、目覚ましい成果をあげてきましたが、あまりにパワフルな手法で、極めて特許性の高いInnovationの発想が次々と出るために、一般公開するワークショップをすることが難しく、ゴールドラットグループの顧客向けにのみ、クローズな環境で開催されてきました。今回のTOCクラブでは、このプロセスを紹介します。
TOC for Innovationのプロセスはシンプルに、以下の質問から始めます。
「クライアントにとって、極めて重大な要望、しかも競合が簡単にマネできない要望とは何か?」
この問いに答えるために、次のプロセスで新たな発想を導きだします。
- 顧客の目ーマイナスから逆転の発想をする
- 市場の目ープラスからの飛躍の発想をする
- 商品の目ー商品パラメターを大きく振る
- WOWメーターでイノベーションの大きさをチェックする
- 変化に対する4つの考察
- 市場への教育
すべてのプロセスが、革新的な発想を導きだすとともに、それをさらに尖らせることが可能。WOW!と言われる商品の企画を磨き上げるプロセスです。
私自身もハイテクの技術企画、商品企画をやってきたマーケターでした。
一般に、企業の企画プロセスは、さまざまなゲート(関門)があり、それが企画の質を高め、事業化するために活用されていますが、本当に役に立っているのでしょうか?
- コストはどうなんだ?
- 競合はどうなっているんだ?
- 差別化はどこでするんだ?
- 事業性はどうなんだ?
- 市場は本当にあるのか?
- いったいどんな人が買ってくれるのか?
こういった企画プロセスでありがちな議論は、基本的には企画をより練り上げるためのものだと思って行われるものですが、実際には、現場のモチベーションを下げてしまったり、とにかく企画を通すために、コスト検討ばっかりに終始してしまい、当初の企画のエッジが削がれてしまい、ユーザーの心に刺さらない企画に落ち着いてしまうことも少なくありません。
TOC for Innovationで変えるのは、企画のマネジメントプロセスそのものです。尖った発想を、磨き上げ、鍛え上げることで、世の中にない価値をもたらすイノベーションを実現するため、経営陣もフルサポートできる環境を作っていきます。しかも、組織の未来を支える「商品で語る中期経営計画」までできてしまいます。
新しい発想をいかに創り、鍛え上げるか、その手があったか!と思えるTOCらしい、シンプルなプロセス。きっとワクワクしていただけるものと思います。
「プロセスさえあれば誰でも世界を変えるイノベーターなれる」
そう信じられる知識体系をご紹介したいと思っています。
2018年01月25日【名古屋】
2018年03月19日【東京】
2018年07月04日【広島】
2018年03月19日【東京】
2018年07月04日【広島】
ソフトウェア開発の本当の制約とは何か?
ソフトウェアの開発の本当のボトルネックとは何でしょうか?
ソフトウェアの開発にTOC流のプロジェクトマネジメントCCPM(Critical Chain Project Management)が導入され、日本のみならず世界中で目覚ましい成果が出ているのはご存知の通りです。
などなど、たくさんの目覚ましい成果を出しているのは幅広く世の中に知られています。
でも、それが本当に問題を解決しているのでしょうか?
実際に、プロジェクトの遅れの原因を調べてみると、遅れの理由のほとんどがあいまいな仕様、仕様決定の遅れ、仕様変更などによることに気づかされます。
ソフトウェア開発に関して、プロジェクトマネジメント以前の問題として仕様が決められないという長年未解決の問題があるのはいまさら言うまでもありません。IT産業界には「銀の弾丸はない」という定説まで作られるほどで、これが本当のボトルネックとも考えられます。
CCPMをやらなくても、AGILEをやらなくても、本当は要件定義さえしっかりしていれば、無駄な手直しをしなくてもソフトウェア開発はうまくいくとも言えます。なぜならば、プロジェクトの遅れの理由のほとんどは、本当は仕様変更で、しかも、それはユーザーは何をしたいかわからないという課題から来ているのではないでしょうか?
逆に言えば、「ユーザーさえ言葉に表せない本当の要望を明らかする」ことが本当の問題解決につながるとも言えます。
TOCはそれぞれの産業界において、長年未解決の問題にブレークスルーを引き起こしてきました。ご存知のようにもともとゴールドラット博士はソフトウェア開発者です。今回は、ソフトウェア開発におけるTOC流の要件定義の知識体系について、紹介したいと思っています。
WOW!とユーザーに言わせる価値に集中したTOC流ソフトウェア要件定義プロセス
E4V (Eyes for Value) Value Driven software requirement definition process in TOC way
ユーザーのWOW!が見える本当の要望さえ定義できれば、ソフトウェア技術者はコードを書きたくてたまらなくなる。そんなプロセスをご紹介します。
ソフトウェアの開発にTOC流のプロジェクトマネジメントCCPM(Critical Chain Project Management)が導入され、日本のみならず世界中で目覚ましい成果が出ているのはご存知の通りです。
- 工期が劇的に短くなった
- 残業がなくなった
- 黙っていても組織の壁を越えて助け合うようになった
- 成果は出たのはうれしいが、何よりもうれしいのは人の成長。こういう現場にしたかったんだ!
などなど、たくさんの目覚ましい成果を出しているのは幅広く世の中に知られています。
でも、それが本当に問題を解決しているのでしょうか?
実際に、プロジェクトの遅れの原因を調べてみると、遅れの理由のほとんどがあいまいな仕様、仕様決定の遅れ、仕様変更などによることに気づかされます。
ソフトウェア開発に関して、プロジェクトマネジメント以前の問題として仕様が決められないという長年未解決の問題があるのはいまさら言うまでもありません。IT産業界には「銀の弾丸はない」という定説まで作られるほどで、これが本当のボトルネックとも考えられます。
CCPMをやらなくても、AGILEをやらなくても、本当は要件定義さえしっかりしていれば、無駄な手直しをしなくてもソフトウェア開発はうまくいくとも言えます。なぜならば、プロジェクトの遅れの理由のほとんどは、本当は仕様変更で、しかも、それはユーザーは何をしたいかわからないという課題から来ているのではないでしょうか?
逆に言えば、「ユーザーさえ言葉に表せない本当の要望を明らかする」ことが本当の問題解決につながるとも言えます。
TOCはそれぞれの産業界において、長年未解決の問題にブレークスルーを引き起こしてきました。ご存知のようにもともとゴールドラット博士はソフトウェア開発者です。今回は、ソフトウェア開発におけるTOC流の要件定義の知識体系について、紹介したいと思っています。
WOW!とユーザーに言わせる価値に集中したTOC流ソフトウェア要件定義プロセス
E4V (Eyes for Value) Value Driven software requirement definition process in TOC way
ユーザーのWOW!が見える本当の要望さえ定義できれば、ソフトウェア技術者はコードを書きたくてたまらなくなる。そんなプロセスをご紹介します。
2017年11月24日【京都】
2017年12月04日【東京】
2017年12月04日【東京】
SKYACTIV開発秘話 マツダにおけるTOC/CCPM事例講演
実は先週、マツダに行って、TOCの活動進捗の報告を受けました。
本当に私自身も想像以上だったのが、ロードスターの開発です。大ヒットしているマツダの新型ロードスターですが、この開発にTOCが徹底的に活用されています。
開発がスタートしたのは、資金繰りに行き詰った経営危機の渦中です。金なし、時間なし、人なしという三重苦を抱えながらも、
この苦境のなか、飛躍的な成長の道筋をつくった現場の生々しい話をしていただきました。
マツダ ロードスターの紹介ページ
一切妥協しない走り、デザイン、そして、関係者を驚かせるインパクトある250万を切るSモデルの価格設定。
しかも、乗れば一発でわかるハイパフォーマンス。
世界中を驚かせ、大ヒットしているのもうなづけます。
このロードスターの心臓ともいえるパワートレインの開発を率いた若狭氏が、どうやってCCPMを徹底活用したか、7月4日、京都の弊社のセミナ―ハウス「楽月庵」で再度お話をしていただけることになりました。
ゆっくりとお話をしていただきたいため、限定50名のみにお声をかけさせていただくことにしました。
岸良も、CCPMを長年やってきましたが、これほどまでに魂のこもった、熱いCCPMの実践は見たことがありません。
若狭氏には、現場のナマナマしいお話をたっぷりとお話をいただき、さらに、ロードスターの展示試乗までできるように特別にお取り計らい頂いております。
場所ですが、京都大原にある弊社楽月庵で、14時から行います。14-16時 マツダロードスター開発秘話16-18時 展示試乗会、ならびに交流会極めて厳しい苦境のど真ん中で、どうやって将来の飛躍の道を切り拓いたか。現場の本音のぶっちゃけトークもしていただきます。
価格低下が止まらないレッドオーシャンの中で、地に落ちたブランドを再構築してきたグローバルマーケティングのトップ青山執行役も来られます。
画期的なイノベーションの発想、そして、それを超短期間で実現する魂のこもった工程表。そしてTOCによる文化の変化。それを実現するための生々しいノウハウの数々。
なんと、NHKのプロフェッショナルにも出たエンジンに革命をもたらしたという世界的に有名な人見常務も、この会にかけつけてくれます。本当にまたとない機会かと思っております。
本当に私自身も想像以上だったのが、ロードスターの開発です。大ヒットしているマツダの新型ロードスターですが、この開発にTOCが徹底的に活用されています。
開発がスタートしたのは、資金繰りに行き詰った経営危機の渦中です。金なし、時間なし、人なしという三重苦を抱えながらも、
この苦境のなか、飛躍的な成長の道筋をつくった現場の生々しい話をしていただきました。
マツダ ロードスターの紹介ページ
一切妥協しない走り、デザイン、そして、関係者を驚かせるインパクトある250万を切るSモデルの価格設定。
しかも、乗れば一発でわかるハイパフォーマンス。
世界中を驚かせ、大ヒットしているのもうなづけます。
このロードスターの心臓ともいえるパワートレインの開発を率いた若狭氏が、どうやってCCPMを徹底活用したか、7月4日、京都の弊社のセミナ―ハウス「楽月庵」で再度お話をしていただけることになりました。
ゆっくりとお話をしていただきたいため、限定50名のみにお声をかけさせていただくことにしました。
岸良も、CCPMを長年やってきましたが、これほどまでに魂のこもった、熱いCCPMの実践は見たことがありません。
若狭氏には、現場のナマナマしいお話をたっぷりとお話をいただき、さらに、ロードスターの展示試乗までできるように特別にお取り計らい頂いております。
場所ですが、京都大原にある弊社楽月庵で、14時から行います。14-16時 マツダロードスター開発秘話16-18時 展示試乗会、ならびに交流会極めて厳しい苦境のど真ん中で、どうやって将来の飛躍の道を切り拓いたか。現場の本音のぶっちゃけトークもしていただきます。
価格低下が止まらないレッドオーシャンの中で、地に落ちたブランドを再構築してきたグローバルマーケティングのトップ青山執行役も来られます。
画期的なイノベーションの発想、そして、それを超短期間で実現する魂のこもった工程表。そしてTOCによる文化の変化。それを実現するための生々しいノウハウの数々。
なんと、NHKのプロフェッショナルにも出たエンジンに革命をもたらしたという世界的に有名な人見常務も、この会にかけつけてくれます。本当にまたとない機会かと思っております。
2015年07月04日【京都】
「イノベーション発想法」 TOC FOR INNOVATION
今回のTOCクラブは、特別です。TOC流のInnovation発想法、TOC for Innovationをテーマにします。
あらゆる産業界で目覚ましいブレークスルーを引き起こしてきているTOCですが、そのブレークスルーの発想をいかに行うかということについて、ゴールドラット博士のブレークスルーの発想をたどり開発されたのが、TOC for Innovationです。
この発想法は、今まであらゆる産業界で実践され、目覚ましい成果をあげてきましたが、あまりにパワフルな手法で、特許性の高いInnovationの発想が次々と出るために、一般公開するワークショップをすることが難しく、ゴールドラットグループの顧客向けにのみ、クローズな環境で開催されてきました。
TOC for Innovationのプロセスはシンプルに、以下の質問から始めます。
「クライアントにとって、極めて重大な要望、しかも競合が簡単にマネできない要望とは何か?」
この問いに答えるために、次のプロセスで新たな発想を導きだします。
すべてのプロセスが、革新的な発想を導きだすとともに、それをさらに尖らせることが可能。WOWと言われる商品の企画を磨き上げるプロセスです。
私自身もハイテクの技術企画、商品企画をやってきたマーケターでした。
一般に、企業の企画プロセスは、さまざまなゲート(関門)があり、それが企画の質を高め、事業化するために活用されていますが、本当に役に立っているのでしょうか?
こういった企画プロセスでありがちな議論は、基本的には企画をより練り上げるためのものだと思って行われるものですが、実際には、現場のモチベーションを下げてしまったり、とにかく企画を通すために、コスト検討ばっかりに終始してしまい、当初の企画のエッジが削がれてしまい、ユーザーの心に刺さらない企画に落ち着いてしまうことも少なくありません。
TOC for Innovationで変えるのは、企画のマネジメントプロセスそのものです。尖った発想を、磨き上げ、鍛え上げることで、世の中にない価値をもたらすイノベーションを実現するため、経営陣もフルサポートできる環境を作っていきます。
新しい発想をいかに創り、鍛え上げるか、その手があったか!と思えるTOCらしい、シンプルなプロセス。きっとワクワクしていただけるものと思います。
あらゆる産業界で目覚ましいブレークスルーを引き起こしてきているTOCですが、そのブレークスルーの発想をいかに行うかということについて、ゴールドラット博士のブレークスルーの発想をたどり開発されたのが、TOC for Innovationです。
この発想法は、今まであらゆる産業界で実践され、目覚ましい成果をあげてきましたが、あまりにパワフルな手法で、特許性の高いInnovationの発想が次々と出るために、一般公開するワークショップをすることが難しく、ゴールドラットグループの顧客向けにのみ、クローズな環境で開催されてきました。
TOC for Innovationのプロセスはシンプルに、以下の質問から始めます。
「クライアントにとって、極めて重大な要望、しかも競合が簡単にマネできない要望とは何か?」
この問いに答えるために、次のプロセスで新たな発想を導きだします。
- 顧客の目ーマイナスから逆転の発想をする
- 市場の目ープラスからの飛躍の発想をする
- 商品の目ー商品パラメターを大きく振る
- WOWメーターでイノベーションの大きさをチェックする
- 変化に対する4つの考察
- 市場への教育
すべてのプロセスが、革新的な発想を導きだすとともに、それをさらに尖らせることが可能。WOWと言われる商品の企画を磨き上げるプロセスです。
私自身もハイテクの技術企画、商品企画をやってきたマーケターでした。
一般に、企業の企画プロセスは、さまざまなゲート(関門)があり、それが企画の質を高め、事業化するために活用されていますが、本当に役に立っているのでしょうか?
- コストはどうなんだ?
- 競合はどうなっているんだ?
- 差別化はどこでするんだ?
- 事業性はどうなんだ?
- 市場は本当にあるのか?
- いったいどんな人が買ってくれるのか?
こういった企画プロセスでありがちな議論は、基本的には企画をより練り上げるためのものだと思って行われるものですが、実際には、現場のモチベーションを下げてしまったり、とにかく企画を通すために、コスト検討ばっかりに終始してしまい、当初の企画のエッジが削がれてしまい、ユーザーの心に刺さらない企画に落ち着いてしまうことも少なくありません。
TOC for Innovationで変えるのは、企画のマネジメントプロセスそのものです。尖った発想を、磨き上げ、鍛え上げることで、世の中にない価値をもたらすイノベーションを実現するため、経営陣もフルサポートできる環境を作っていきます。
新しい発想をいかに創り、鍛え上げるか、その手があったか!と思えるTOCらしい、シンプルなプロセス。きっとワクワクしていただけるものと思います。
2015年04月23日【東京】
2015年05月12日【京都】
2015年05月12日【京都】
TOC流イノベーション発想法
あらゆる産業界で目覚ましいブレークスルーを引き起こしてきているTOCですが、そのブレークスルーの発想をいかに行うかということについて、ゴールドラット博士のブレークスルーの発想をたどり開発されたのが、TOC for Innovationです。
この発想法は、今まであらゆる産業界で実践され、目覚ましい成果をあげてきましたが、あまりにパワフルな手法で、極めて特許性の高いInnovationの発想が次々と出るために、一般公開するワークショップをすることが難しく、ゴールドラットグループの顧客向けにのみ、クローズな環境で開催されてきました。
TOC for Innovationのプロセスはシンプルに、以下の質問から始めます。
「クライアントにとって、極めて重大な要望、しかも競合が簡単にマネできない要望とは何か?」
この問いに答えるために、次のプロセスで新たな発想を導きだします。
すべてのプロセスが、革新的な発想を導きだすとともに、それをさらに尖らせることが可能。WOWと言われる商品の企画を磨き上げるプロセスです。
私自身もハイテクの技術企画、商品企画をやってきたマーケターでした。
一般に、企業の企画プロセスは、さまざまなゲート(関門)があり、それが企画の質を高め、事業化するために活用されていますが、本当に役に立っているのでしょうか?
こういった企画プロセスでありがちな議論は、基本的には企画をより練り上げるためのものだと思って行われるものですが、実際には、現場のモチベーションを下げてしまったり、とにかく企画を通すために、コスト検討ばっかりに終始してしまい、当初の企画のエッジが削がれてしまい、ユーザーの心に刺さらない企画に落ち着いてしまうことも少なくありません。
TOC for Innovationで変えるのは、企画のマネジメントプロセスそのものです。尖った発想を、磨き上げ、鍛え上げることで、世の中にない価値をもたらすイノベーションを実現するため、経営陣もフルサポートできる環境を作っていきます。
新しい発想をいかに創り、鍛え上げるか、その手があったか!と思えるTOCらしい、シンプルなプロセス。きっとワクワクしていただけるものと思います。
この発想法は、今まであらゆる産業界で実践され、目覚ましい成果をあげてきましたが、あまりにパワフルな手法で、極めて特許性の高いInnovationの発想が次々と出るために、一般公開するワークショップをすることが難しく、ゴールドラットグループの顧客向けにのみ、クローズな環境で開催されてきました。
TOC for Innovationのプロセスはシンプルに、以下の質問から始めます。
「クライアントにとって、極めて重大な要望、しかも競合が簡単にマネできない要望とは何か?」
この問いに答えるために、次のプロセスで新たな発想を導きだします。
- 顧客の目ーマイナスから逆転の発想をする
- 市場の目ープラスからの飛躍の発想をする
- 商品の目ー商品パラメターを大きく振る
- WOWメーターでイノベーションの大きさをチェックする
- 変化に対する4つの考察
- 市場への教育
すべてのプロセスが、革新的な発想を導きだすとともに、それをさらに尖らせることが可能。WOWと言われる商品の企画を磨き上げるプロセスです。
私自身もハイテクの技術企画、商品企画をやってきたマーケターでした。
一般に、企業の企画プロセスは、さまざまなゲート(関門)があり、それが企画の質を高め、事業化するために活用されていますが、本当に役に立っているのでしょうか?
- コストはどうなんだ?
- 競合はどうなっているんだ?
- 差別化はどこでするんだ?
- 事業性はどうなんだ?
- 市場は本当にあるのか?
- いったいどんな人が買ってくれるのか?
こういった企画プロセスでありがちな議論は、基本的には企画をより練り上げるためのものだと思って行われるものですが、実際には、現場のモチベーションを下げてしまったり、とにかく企画を通すために、コスト検討ばっかりに終始してしまい、当初の企画のエッジが削がれてしまい、ユーザーの心に刺さらない企画に落ち着いてしまうことも少なくありません。
TOC for Innovationで変えるのは、企画のマネジメントプロセスそのものです。尖った発想を、磨き上げ、鍛え上げることで、世の中にない価値をもたらすイノベーションを実現するため、経営陣もフルサポートできる環境を作っていきます。
新しい発想をいかに創り、鍛え上げるか、その手があったか!と思えるTOCらしい、シンプルなプロセス。きっとワクワクしていただけるものと思います。
2016年07月22日【京都】
2016年08月25日【東京】
2016年08月25日【東京】
研究開発企業のためのTOC
極めて不確実性の高い、技術的難易度の瓦解、研究開発でもTOCは幅広く活用されています。
こういった課題を解決するための知識体系がTOCには蓄積されています。これが「戦略と戦術のツリー」という知識体系です。「戦略と戦術のツリー」の素晴らしいところは、単なる問題解決の知識体系だけでなく、組織に長年染みついた既成概念を一つひとつ変えていくことにより飛躍的な成長を組織にもたらすために手順まで丁寧に定義していることです。
この「戦略と戦術のツリー」は、岸良裕司の著作『全体最適の問題解決入門』に書かれていますが、その詳細の内容については、あまり知られておりません。
今回は、TOCの知識体系のすべてが詰まった「戦略と戦術のツリー」を紹介しながら、研究開発が事業活動の核ともいえる、製薬企業に適用し、目覚ましい事例を出した企業の経営幹部にも来ていただき、事例を発表して頂く予定です。
既成概念をいかにして変えてきたか、実践してきた本人たちから聞くことで、多くの学びが得られ、きっとワクワクしていただけるのではないかと・・・
科学論文のように、理論と実証成果とセットにしています。ハードサイエンスをベースとした本当にTOCらしい、TOCクラブになりそうです。
- いかにして研究開発のスピードを上げるか
- 外部に依存したタスクをいかに無理なく短縮するか
- 一人ひとりの生産性をいかに上げるか
- 投資なしに、研究開発のキャパシティをいかに上げるか
- 設備投資なしに生産キャパシティを上げるか
こういった課題を解決するための知識体系がTOCには蓄積されています。これが「戦略と戦術のツリー」という知識体系です。「戦略と戦術のツリー」の素晴らしいところは、単なる問題解決の知識体系だけでなく、組織に長年染みついた既成概念を一つひとつ変えていくことにより飛躍的な成長を組織にもたらすために手順まで丁寧に定義していることです。
この「戦略と戦術のツリー」は、岸良裕司の著作『全体最適の問題解決入門』に書かれていますが、その詳細の内容については、あまり知られておりません。
今回は、TOCの知識体系のすべてが詰まった「戦略と戦術のツリー」を紹介しながら、研究開発が事業活動の核ともいえる、製薬企業に適用し、目覚ましい事例を出した企業の経営幹部にも来ていただき、事例を発表して頂く予定です。
既成概念をいかにして変えてきたか、実践してきた本人たちから聞くことで、多くの学びが得られ、きっとワクワクしていただけるのではないかと・・・
- 戦略と戦術のツリーの紹介
- 実証成果
科学論文のように、理論と実証成果とセットにしています。ハードサイエンスをベースとした本当にTOCらしい、TOCクラブになりそうです。
2015年08月21日【大阪】
ラミ・ゴールドラット 「不確実性をどう取り扱うか」
ゴールドラット博士の息子でもあり、
今回のセミナーでは、複雑で、不確実性があり、ジレンマがある現実 の中で、いかに目標を達成しつづけるか、新しい知見を公開します。
「不確実性をどう取り扱うか」
ラミ・ゴールドラット ゴールドラットグループCEO
ラミ・ゴールドラットの強みはなんといっても「わかりやすさ」です。
ともすれば、深く哲学的なゴールドラット博士の話について周囲から説明を求められているうちに、彼は、ゴールドラット博士が 語る論理の飛躍を埋めて、誰でもわかるようにやさしく説明するという、とても素晴らしいスキルを鍛えられてきました。
今回の洞察も、ゴールドラット博士が亡くなる直前に遺した絶筆「マネジメントの科学」という洞察を発展させ、複雑で、 不確実性があり、ジレンマがある現実の中で、いかに目標を達成しつづけるかについて、シンプルで実践的な方法をご紹介します。いかにもTOCらしい実践的な方法論なので、多くの方々で 得られることは多いかと思っています。
マネジメントの科学
https://www.youtube.com/watch?v=JQkqj0vOwBs
特にマネジメントに関する3つの根本的な誤りの考察は秀逸です。不確実性について、根本的な前提の誤りによって引き起こされる現実の数々の問題。それをいかにシンプルに対処していくかが明らかにされます。
- 断わりきれない提案 (URO: UnRefusable Offer)、
- 教育のためのTOC (TOCfE: TOC for Education)、
- 戦略と戦術のツリー (S&T Tree: Strategy and Tactics Tree)
今回のセミナーでは、複雑で、不確実性があり、ジレンマがある現実 の中で、いかに目標を達成しつづけるか、新しい知見を公開します。
「不確実性をどう取り扱うか」
ラミ・ゴールドラット ゴールドラットグループCEO
ラミ・ゴールドラットの強みはなんといっても「わかりやすさ」です。
ともすれば、深く哲学的なゴールドラット博士の話について周囲から説明を求められているうちに、彼は、ゴールドラット博士が 語る論理の飛躍を埋めて、誰でもわかるようにやさしく説明するという、とても素晴らしいスキルを鍛えられてきました。
今回の洞察も、ゴールドラット博士が亡くなる直前に遺した絶筆「マネジメントの科学」という洞察を発展させ、複雑で、 不確実性があり、ジレンマがある現実の中で、いかに目標を達成しつづけるかについて、シンプルで実践的な方法をご紹介します。いかにもTOCらしい実践的な方法論なので、多くの方々で 得られることは多いかと思っています。
マネジメントの科学
https://www.youtube.com/watch?v=JQkqj0vOwBs
特にマネジメントに関する3つの根本的な誤りの考察は秀逸です。不確実性について、根本的な前提の誤りによって引き起こされる現実の数々の問題。それをいかにシンプルに対処していくかが明らかにされます。
2014年09月17日【東京】
組織に長年染みついた既成概念をいかに変えるか?
おかげさまで、『ザ・ゴール コミック版』が全国の書店でナンバーワンのベストセラーとなり、本当に感謝しています。
今年は、全体最適の和が一気に広がる一年にしたいと・・・
さて今回のTOCクラブのテーマは、「組織に長年染みついてきた既成概念をいかに変えるか?」です。
昨年12月17日ー18日開催されたTOCサミットで次々と紹介された様々な分野での目覚ましい事例に驚かれた方々は
少なくないかと思います。これらの数々の唯一の共通点は、「組織に長年染みついてきた既成概念を変えたこと」と言ってもよいかと思います。
今回の、この「既成概念をいかに変えるか」というTOCのコア中のコアを課題を真正面から議論していたきいと思います。
講師は、ゴールドラット博士と25年間一緒に活動し、そして、TOCのもっとも重要な柱である思考プロセスの開発者の一人、また、様々な博士の知識体系を世界中に伝えてきたTOCの第一人者中の第一人者、TOCの国際資格認定機関TOC-ICOの元会長でもあるリサ・シェインコフです。
昨年の来日講演でも、ゴールドラット博士と歩んだ25年間の道のりと自身の成長の過程、博士からの学びを語ってくれ、多くの方々の共感と感動をよんだのは記憶に新しいかと思います。
リサのすごいところは、博士の発明を誰でもできるプロセスに落とし込めること。彼女のプレゼンは、いつでも、やさしく、そして、わかりやすい。
そのやさしさは、彼女の人柄から来ているのかとも思っています。
本当にすばらしい人です。
今年は、全体最適の和が一気に広がる一年にしたいと・・・
さて今回のTOCクラブのテーマは、「組織に長年染みついてきた既成概念をいかに変えるか?」です。
昨年12月17日ー18日開催されたTOCサミットで次々と紹介された様々な分野での目覚ましい事例に驚かれた方々は
少なくないかと思います。これらの数々の唯一の共通点は、「組織に長年染みついてきた既成概念を変えたこと」と言ってもよいかと思います。
今回の、この「既成概念をいかに変えるか」というTOCのコア中のコアを課題を真正面から議論していたきいと思います。
- 組織にはびこる典型的な既成概念
- なぜ、既成概念が生まれるのか?
- 既成概念を変える、TOC流のシンプルな方法
- 目覚ましい事例
講師は、ゴールドラット博士と25年間一緒に活動し、そして、TOCのもっとも重要な柱である思考プロセスの開発者の一人、また、様々な博士の知識体系を世界中に伝えてきたTOCの第一人者中の第一人者、TOCの国際資格認定機関TOC-ICOの元会長でもあるリサ・シェインコフです。
昨年の来日講演でも、ゴールドラット博士と歩んだ25年間の道のりと自身の成長の過程、博士からの学びを語ってくれ、多くの方々の共感と感動をよんだのは記憶に新しいかと思います。
リサのすごいところは、博士の発明を誰でもできるプロセスに落とし込めること。彼女のプレゼンは、いつでも、やさしく、そして、わかりやすい。
そのやさしさは、彼女の人柄から来ているのかとも思っています。
本当にすばらしい人です。
2015年02月05日【京都】
|
|